こんにちは、まさおです。
今回は、「節税って実際どれくらい効くの?」という疑問に答えるべく、我が家のリアルな税金ビフォーアフターをご紹介します。
私たちは夫婦共働きで、子どもはいない家庭です。派手な節税テクニックは使っていません。ふるさと納税とiDeCoという基本中の基本だけ。でも、それだけで年間約20万円以上、税金が減りました。
さらに今回は、「え、そんなことで節税できるの!?」という知ってる人だけ得する“プチ節税ネタ”も後半にまとめています。ぜひ最後まで読んで、明日からの家計改善に役立ててください!
1. 節税前の我が家:何もしてなければ、けっこう持っていかれてた件
まずは我が家のスペックからお話しますね。
- 家族構成:夫婦2人(共働き)
- 年収:夫800万円、妻400万円
- 子ども:なし
- 持ち家:なし(住宅ローン控除は対象外)
ということで、特に大きな控除があるわけでもなく、まっすぐ税金が襲いかかってくる構成です。
ざっくりですが、私(夫)の所得税+住民税の合計は年間で約84万円程度になる試算でした。
2. やったのは2つだけ。でも効果はしっかり
面倒な手続きは嫌だったので、最初に着手したのは「簡単だけど効果がある」ものだけに絞りました。
🟢ふるさと納税
- 利用自治体数:10自治体程度
- 選んだ返礼品:冷凍食品、肉、日用品など
- 寄付額:約13万円(上限いっぱい)
- 控除額:約128,000円(自己負担2,000円を除く)
もらえるものはもらって、納税額は下げられる。まさにWin-Win制度です。
🟢iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 掛金:月20,000円 × 12ヶ月 = 年間240,000円
- 控除額:所得税20%+住民税10% = 30% → 240,000円 × 0.30 = 72,000円
積立は給与から天引き。強制的に貯金できて、かつ節税になるのが魅力。
🟢節税効果まとめ
| 節税策 | 内容 | 節税効果(概算) |
|---|---|---|
| ふるさと納税 | 食品・日用品など10自治体 | 約128,000円 |
| iDeCo(夫) | 月2万円積立×12ヶ月 | 約72,000円 |
| 合計 | 約200,000円 |
3. 税金ビフォーアフター比較表
| 項目 | 対策なし | 対策あり | 差額 |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 約410,000円 | 約338,000円 | ▼72,000円 |
| 住民税 | 約430,000円 | 約302,000円 | ▼128,000円 |
| 合計 | 約840,000円 | 約640,000円 | ▼200,000円 |
※この数字はあくまで概算です。
| 制度 | 毎月の手取り増える? | 確定申告で戻る? | タイミング |
|---|---|---|---|
| iDeCo | ❌(会社員は年末調整 or 翌年住民税減額) | ⭕(年末調整か確定申告) | 年末調整時 or 確定申告後 |
| ふるさと納税(ワンストップ) | ⭕(翌年6月〜住民税減額) | ❌ | 翌年度の12か月間 |
| ふるさと納税(確定申告) | ⭕(翌年6月〜住民税減額) | ⭕(申告後に所得税還付) | 翌年度+申告後1〜2か月 |
4. やってみて気づいたこと・反省点
- iDeCoは控除より“強制貯金”の意味が大きい:給与天引きで積み立てられるので、浪費の抑制にもつながりました。
- ふるさと納税は返礼品選びが楽しくてクセになる:冷凍庫との相談が大事。うちはキャパオーバー気味でした(笑)
- 証明書の提出や申請期限をちゃんと確認すること:医療費控除などは領収書管理が重要。忘れると効果ゼロです。
5. 今年の向けた反省と戦略
まだまだ節税の余地はあると感じています。たとえば:
- 妻のiDeCoも始める(さらに節税可能)
- 医療費控除の活用(出産関連など)
- 新NISA制度を家計と連動させて効率化
「節税」と「貯蓄」「資産形成」は切り離せないなと実感しています。
6. ついでに覚えておくと得する「プチ節税ネタ」集
ここからは、「知ってるか知らないか」で差が出る、ちょっとマニアックだけど役立つ節税ポイントを紹介します!
働き方・タイミングで変わる節税術
- 4〜6月の残業は控えめに:社会保険料の計算対象はこの時期の給与。残業が多いと、1年間ずっと高い保険料を払うことに。
- 通勤手当は非課税限度額に注意:月15万円まで非課税。それ以上は課税対象になる可能性あり。
- 副業収入が20万円以下なら確定申告不要:ただし住民税の申告は必要。副業バレにも注意が必要。
ライフイベントと節税のつながり
- 医療費控除の対象は思ったより広い:通院の交通費も対象になるし、出産費用も対象。
- 扶養に入れるタイミングは“年末”がカギ:年末時点で扶養していれば、その年は控除が適用される。
- 大学に通う社会人は経費化できるかも?:自営業や法人なら、通信制大学・大学院の学費が経費になる可能性も。
お金の使い方も見直してみる
- iDeCoとNISA、どっちを優先?:節税目的ならiDeCoだけど、60歳まで引き出せない。家計の流動性も考慮しよう。
- ふるさと納税は“全力OK”:上限額までは迷わず突っ込んでよし。返礼品も楽しめる。
7. まとめ|節税は“やった人だけが得をする”世界
節税というのは、決して裏技ではなく、制度を理解して正しく使えば誰でもできる“生活防衛”の方法です。
大きく稼げなくても、支出を抑えることで実質的に手取りを増やすことができます。
そして、節税は知識だけじゃなく“行動”がカギ。この記事を読んで「うちもやってみようかな」と思ってもらえたら嬉しいです!
以上、共働き夫婦がリアルに取り組んだ節税ビフォーアフターと、小ワザ集のご紹介でした!
ぜひ、あなたの家庭にも合った節税法を見つけて、家計の“防御力”を高めていきましょう

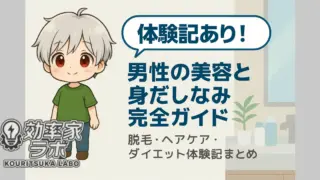


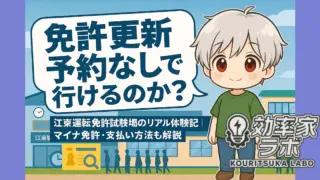





コメント