あなたは「12月に子どもが生まれるのは、税制・社会保険料・育休の観点から最高のタイミングだ」という噂を聞いたことがありますか?でも実際にどうすれば得するのか、具体的な手順や考え方を教えてくれる人は少ないですよね。
この記事では、私たち夫婦(年収は夫800万円・妻400万円)が「12月出産×育休戦略×年子」というトリプルコンボを活用し、短期的に最大限得をするために実際に組んだ計画と考え方をリアルに解説します。
あなたも知っている「社会保険料」の重い負担
給与明細を見たとき、「社会保険料の高さ」に思わずため息が出ませんか?特にボーナス月の社会保険料の引かれ方は強烈。額面100万円の賞与でも社会保険料で15万円、所得税も15万円と、手元に残るのは激減します。
そこで、私たちは賞与月の社会保険料をなんとか減らすべく、育休取得スケジュールを計算し尽くしました。
あなたの好奇心をそそる「12月出産×育休スケジュール」の仕組み
我が家の場合、妻は10月から産前休業に入り実家へ里帰り。私は12月初旬から有給休暇を取得しました。そして12月中旬の出産直後から28日間の出生時育児休業を取得、そのまま1月末まで育休に入ることで、「賞与月をまたぐ1ヶ月超の育休」を実現。
なぜ「1ヶ月超」なのかというと、実は賞与月の社会保険料をゼロにするには、「賞与月の月末を含む、かつ1ヶ月超」の育休取得が必須条件だからです。短期の育休だけではダメなのです。
さらに朗報です。従来は「月末に育休取得中でないと社会保険料免除にならない」というルールでしたが、現在は「月内に14日以上取得すれば免除される」という新ルールが適用されています。つまり、1月に14日、2月に14日分割取得すれば、2ヶ月分の社会保険料が丸ごと免除されるのです!
あなたも怒りを感じるかもしれない「税制・手当の理不尽」
しかし一方で、納得できない制度の理不尽さにも直面しました。例えば、育休中の妻が収入激減でも夫の扶養に入れないという謎の壁。さらには株式投資で損失を出した場合、その損失は手当に反映されず、得したときだけペナルティとして手当が減額されるという理不尽さ。
児童手当をはじめ多くの手当の所得制限は最近撤廃されましたが、それでも制度間の不公平感は解消されていません。実際、まだ扶養の壁や損失補填の仕組みが不十分であり、利益が出た時だけ不利益を被るという構造自体が解消されていないのです。
業界内常識への疑問:年子出産は本当に「最強の戦略」なのか?
よく言われる「年子は育休を連続して使えるから有利」という業界内の常識。しかし実は年子出産は、家庭への負担が爆増し、短期的な金銭メリットのために長期的なキャリアや家庭環境に悪影響を及ぼすこともあります。
もちろん、我が家でも2人目を年子で考える理由はあります。妻が復帰困難な職場環境であるため、育休を延長し時間を稼ぎながら次のキャリアプランをゆっくり検討できるというメリットがあるからです。
しかし、年子出産が必ずしも「得策」でない家庭もあります。長期的なキャリア形成や家庭運営に大きな負担を与える可能性があり、安易に選択するべきではありません。むしろ、家庭ごとの事情に合わせて柔軟に対応する必要があります。
おわりに:あなたも私も、制度の理不尽とどう戦うか?
育休や社会保険料、税金の制度を詳しく知り、うまく活用することは賢明な戦略です。しかし、それだけで十分でしょうか?制度の理不尽さ、子育て支援の矛盾を根本的に問い直す必要もあるのではないでしょうか。
この記事をシェアするあなたが制度の「勝ち組」になるだけでなく、制度の理不尽に目を向け、議論を巻き起こしていくきっかけになれば幸いです。

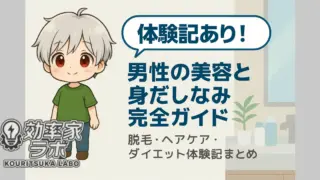


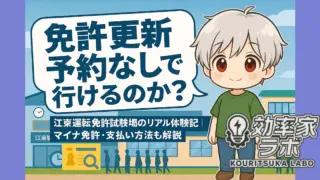






コメント