30代後半。仕事にも慣れ、それなりに成果も出してきた。
部下もできて、プロジェクトを任されるようになり、会社からの評価も悪くない。
だけど、ある日ふと手が止まる。「……このままでいいんだっけ?」
定時後、なんとなく転職サイトを開いては閉じる。
SNSではフリーランスや異業種転職に挑戦する人がキラキラして見える。
一方で、家庭や住宅ローン、今の肩書き――守るものも増えている。
選択肢は多いのに、どれもピンとこない。やりたいことが、わからない。
これは、私自身が30代後半に体験したことだ。
焦る気持ちを抑えながら、自分のキャリアを見つめ直す中で出会ったのが、**「ライフスパン理論」と「内的キャリアの再構築」**という考え方だった。
この記事では、私自身の体験をベースに、
- どんなことで悩んでいたのか
- ライフスパン理論にどう助けられたのか
- 内的キャリアとどう向き合ってきたのか
を振り返っていきます。
「何かを変えたいけど、何を変えればいいかわからない」
そんなモヤモヤを抱える誰かにとって、ヒントになれば嬉しいです。
1. キャリアの“モヤモヤ”は突然やってくる
30代後半。ITエンジニアとして数年キャリアを積み、年収も上がってきた。
成果は出ていたが、役職はつかない。
チームで何かを成し遂げる経験よりも、技術職として1人で粛々と積み上げる仕事が多かった。
孤独ではないが、孤立しているような感覚。
「このまま、誰とも関わらずスキルだけ伸ばしていくのかな」
「年収は上がっても、視野は広がらないままかもしれない」
そんな時、ふと昔の友人から「カフェをやらないか」と誘われた。
正直、ちょっと心が動いた。私は経営や会計が得意だったし、「自分でビジネスを動かす」ことへの興味は強かった。
でも、うまくいかなかった。
方向性の違い、人間関係のズレ。
最終的に、その話は立ち消えになった。
それでも、自分の中には“何かを変えたい”気持ちだけが残った。
このままじゃいけない。けれど、何をしたらいいのかわからない。
やりたいことが、わからない――その状態が、いちばんつらかった。
2. ライフスパン理論で振り返る、自分のキャリア段階
そんなときに出会ったのが、アメリカのキャリア心理学者ドナルド・E・スーパーの「ライフスパン理論」だった。
キャリアは5つの段階に分かれて発達していくというこの理論。
| 段階 | 年齢目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 成長期 | 〜14歳 | 自己概念の形成 |
| 探索期 | 15〜24歳 | 興味や価値観に基づく職業探索 |
| 確立期 | 25〜44歳 | 職業の選定と安定の確立 |
| 維持期 | 45〜64歳 | キャリアの維持と発展 |
| 衰退期 | 65歳以降 | 引退準備、仕事からの離脱 |
当時の私は、ちょうど「確立期」の終盤にいた。
でも、実感として「確立された」感じはまったくなかった。
年収は上がっていた。でも役職もつかないし、マネジメント経験もない。
学ぶ意欲はあったから、マネジメントの本を読んだり、大学院の単科コースにも通った。
でも、どこか空回りしていた。結局、1年も続かなかった。
ちょうどその頃、人生でも大きな変化があった。
今の妻となるパートナーと出会い、価値観や未来について深く考えるようになった。
キャリアを変えるよりも、まず大切な人との関係を築くことが優先になった。
でもどこかに、“自分だけが取り残されている感覚”があった。
あなたは今、どのステージにいると感じていますか?
💡補足:ライフスパン理論には「人生の役割」もある
実はスーパーの理論には、もう一つ重要な視点がある。
それは「人は人生の中で複数の役割(Life Roles)を担う」という考え方だ。
たとえば、「労働者(worker)」だけでなく、
「家庭人(homemaker)」「学習者(learner)」「余暇人(leisurite)」「市民(citizen)」といった
様々な立場を同時に生きており、それらが人生のフェーズによって入れ替わる。
私自身もこの頃、学習者として大学院に通い、家庭人としてパートナーと向き合い、
市民として社会との接点を模索していた。
「キャリア=仕事」ではなく、「キャリア=生き方」だと気づけたのは、
この理論を知っていたからかもしれない。
スーパーは言う。
「キャリア発達は、直線ではなく、人生を通じて何度も“探索”と“確立”を繰り返すプロセスである」
この言葉に、私は救われた気がした。
そうか、まだ“やり直せる”んだ――遅すぎるわけじゃないんだ。
3. 「内的キャリアの再構築」は、手探りで始まった
転職や起業じゃなくても、道はある。
当時の私は、思い切って「異動」を選んだ。
希望を出してマーケティング部門に異動したのが、すべての始まりだった。
ビジネス全体を見渡す機会を得られたのは、大きな収穫だった。
その後、新規事業の部門に声がかかり、今に至る。
チームビルディングやマネジメントの機会は、結局この会社では得られていない。
でも、今は以前よりも確実に、「自分で考え、動ける余白」がある。
「内的キャリア」が少しずつ、再構築されていく感覚があった。
マーケティング部門に異動してから、私はようやく「マーケっぽいこと」に触れることができた。
最初の数ヶ月は、社内外の情報収集やヒアリングが中心だった。
顧客に直接会って、現場のリアルな声を聞くことができたのは貴重な経験だった。
B2Bの世界は、思っていたよりずっと人が優しくて、丁寧で、許容が広かった。
「現場はこんなにも課題にあふれているのに、なぜ会社は動かないんだろう?」と、強く思った。
一方で、壁もすぐに見えた。
社内には「これはうち(メーカー)の仕事じゃない」という空気が漂っていた。
本気で新規事業を作ろうとしている人はほとんどいなかった。
私が出した提案は、評価もされず、支援もされず、ただ「やりたきゃやってみたら?」と丸投げされるだけだった。
組織が動かない。人も動かない。
そんな中で、「動こうとしている自分」がどんどん浮いていく感覚があった。
でも、それでも私はやりたかった。
社内で新規事業のムーブメントを仕掛けたあの試みには、今でも価値があったと感じている。
当時の私は、「なぜ自分はこれをやっているのか?」という問いに、毎日のように向き合っていた。
「やりたいことがわからない」のではなく、「やりたいことを形にできない」ことが苦しかったのだ。
そうして私は、内的キャリア――自分の価値観や納得感、働く意味――を再構築しはじめた。
誰に教えられるでもなく、
ただ「書く」「考える」「試す」――そんな日々だった。
もしかすると、「再構築」とは、誰かに承認されることではなく、自分自身の中で納得することなのかもしれない。
4. キャリア迷子から抜け出すためにやったこと
キャリアに迷っていた時期、私はいくつかの「行動」を通して、自分なりに突破口を探していた。
ひとつは、大学院のプレMBAコースに通い始めたこと。
経営、マーケティング、組織論、心理学――体系的に学べる環境に身を置けば、自分の中で何かが変わるかもしれないと思った。
ただ、それは長くは続かなかった。
その大学は卒業までのハードルが高く、単科とはいえ課題も多い。
仕事の忙しさと重なり、やがて時間を確保できなくなっていった。
さらに追い打ちをかけたのが、コロナ禍の到来だった。
私は、学び以上に「人との出会いやコネクション」を期待していた部分が大きかった。
でも、講義はすべてオンライン。誰とも関われず、モチベーションは静かに落ちていった。
思い返せば、この頃の私は「理想を叶える手段」にこだわりすぎていたのかもしれない。
どこかで“完璧な環境”を求めすぎていた。
完璧な環境なんて、どこにもないのかもしれない――。
そんなことを思い始めた頃、私は異動の話をもらった。
転職までは踏み切れなかったが、私は異動を選んだ。
その決め手は、「新規事業を立ち上げようとしている部署がある」と知ったことと、
以前、社内のトップ層に向けてIT化提案を持ち込んだ経験から、顔を覚えられていたことだった。
実際に異動してからは、顧客との接点を持ち、現場のリアルな課題を聞けた。
とある現場で、担当者がこんな言葉をかけてくれた。
「あなたの提案してくださったシステムで現場の皆さんが便利になったと喜んでいました」
…その一言で、「やっぱり現場って尊い」と実感した。
「自分の仕事が、ちゃんと“誰か”につながっている」と感じられたのは、大きな変化だった。
うまくいったことばかりではない。
提案がスルーされることも、組織の動きの鈍さに絶望することもあった。
それでも現場に出て、自分の手と耳で感じたことは、いまも迷ったときの“灯り”になっている。
5. まとめ:モヤモヤは「再構築」のチャンス
あのとき感じていたキャリアのモヤモヤは、
「このままでいいのか?」という漠然とした不安だった。
でも今なら、それはただの迷いではなく、
内的キャリアを問い直せというサインだったとわかる。
当時の私は、「役職がない」「チームを持てない」「新しいことをやっても評価されない」と思っていた。
だけど本当は――
目に見える実績ではなく、
「誰のために働きたいのか?」
「どんな価値を提供したいのか?」
「自分は仕事を通じて、どんな人生を築きたいのか?」
そういった“意味”の部分に迷っていたのだ。
その問いに、書きながら、考えながら、少しずつ言葉を与えていった。
「人との出会い」が、キャリアの軌道を変えた
大学院に通ったことは、途中でやめたけれど無駄ではなかった。
異動してマーケティングや新規事業に触れた経験は、自分を動かす力になった。
そんな中、私の人生に現れたのが、今のパートナーだった。
最初はゲームがきっかけだったが、真剣に将来を考えるようになり、
遠距離を経て「一緒に暮らす」ことを現実的に見据えはじめた。
私はそのために勤務地を変え、当面は自分が養う覚悟もした。
“自分ひとり”のキャリアではなく、“誰かと生きる”キャリアへと、価値観がシフトしていった。
キャリアは一直線ではない。
Superのライフスパン理論が示すように、人は何度でも「探索」と「確立」を繰り返しながら歩いていく。
だから、モヤモヤしている時期こそ、“キャリアが育つプロセス”だと受け止めていい。
今も私は道の途中にいる。
でも、誰と、どんなふうに働き、生きるのか――
その問いに、少しずつ自分の言葉で答えられるようになってきた。
迷いは、次のフェーズに進むための準備運動だ。
キャリアのモヤモヤに向き合うことは、
「まだここから変われる」と信じる、ひとつの意思表示でもある。
あなたの“再構築”は、どこから始まりそうですか?

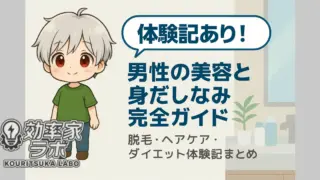


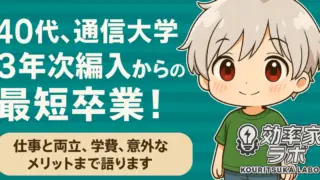



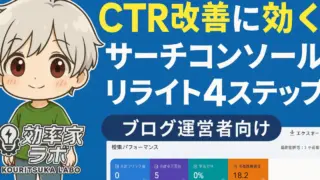


コメント