― 「制度があるのに仕組みがない」現場のリアル ―
■ 育休が決まった。でも、最初に言われたのは「後任どうする?」
4ヶ月後、私は育休に入る予定だ。 職場にも伝え、会社としても制度的には問題なし。 ——なのに、最初に渡されたのは「採用アカウント」だった。
「あなたの代わりの人、社外から採用していいよ。とりあえず探してみて」
え、まさかの「俺がやるのか…?」という気持ちになった。
■ 「小さな会社のなんでも屋」、それって誇っていいのか?
私はIoT商品の企画や、クラウド連携の設計、海外メーカーとの調整(英語・中国語)、 そして現地施工のアドバイスや顧客対応まで、いろんなことを1人でこなしてきた。
小さな組織の中で、自然と“なんでも屋”になっていた。 ありがたいことに、ある程度は評価もされていたと思う。
でも、あなたならどう思うだろう? 「その人がいなくなった時に、すべてが止まる」 そんな仕事の仕方は、本当にいいことなのか?
■ 採用システムにログインしてみた。見えたのは“ズレ”だった
さて、渡されたのは某採用プラットフォームのアカウント。 リクナビのようなシステムで、私は自分の代替要員を探すことになった。
でも、募集要項を見てすぐに違和感があった。
- 想定年収:私の仕事量に対して安すぎる
- 求められるスキル:なぜか“未経験歓迎”と書かれている
- 想定年齢:どう見ても若手向けで、経験者ではなさそう
「これ、誰も来ないやつだろ…」
そう思いながら、応募者の履歴書や推薦状に目を通した。
あなたならどうするだろう? 「自分の代わりにこの人が来るとしたら、安心して任せられるか?」 その判断を、あなた自身が迫られるとしたら?
■ 心が揺れたのは、昔の自分みたいな人
とはいえ、中には少し気になる応募者もいた。 昔、私がインフラエンジニアとして色々やらされていた頃の自分に、少し似ていた。
海外での勤務経験がある人もいた。 「ああ、この人はきっと言葉の壁を乗り越えてきたんだろうな」と感じた。
「任せてみたいな」と思う瞬間も、正直あった。
でも同時に、「あの頃の自分に今の自分の仕事はできただろうか?」 そう思うと、不安もあった。
■ 採用には決定権がない。でも、現場の責任はある
私には採用の最終決定権がない。 でも、もし後任がうまくフィットしなければ、現場が混乱するのは目に見えている。
だから、強く推薦することはできても、責任だけは回ってくる。
「採用には口を出すな。でも、現場はよろしくね」
そんな空気を感じて、違和感を覚えた。
あなたの職場では、どうだろう? 採用と現場の分断が、見えないストレスを生んでいないだろうか?
■ 採用“する側”にも、しんどさと葛藤がある
一方で、採用側(上長や人事)に全く配慮がないわけではない。
- 現場をわかっていない中で、最適な人材を探すプレッシャー
- スピードを求められる一方で、育成や引き継ぎの時間が確保できない不安
- 「今いるメンバーでなんとかして」と言われる恐怖
育休=迷惑ではない。だけど段取りがきついのは事実。 採用側の立場に立つと、これはこれで大変なのだと思う。
だからこそ、私のような“当事者”が情報を整理し、業務を棚卸しして、協力できる余地はある。
「後任探し」を押し付けられたと感じるのではなく、自分の仕事を未来につなげる機会だと捉え直せたら、少しだけ前向きになれるかもしれない。
■ 育休=制度がある。でも、「休める空気」は誰が作る?
私は育休を楽しみにしている。 妻は強めの圧で「絶対取れ。取らんと殺す」と言ってくれた(笑)。 会社も表向きは歓迎ムードだ。
でも実態は、「準備は全部整えてから休んでね」という空気。
「迷惑かけないように休む」って、休みじゃなくて仕事じゃない?
そう言いたくなる気持ちがある。
あなたはどう思う? 制度として「育休」があっても、休む側が“贖罪”のように準備しなければならないのは、健全な状態だろうか?
■ 「人がいなくなること」こそ、組織が強くなるチャンスかもしれない
私は前から、ある考えを持っている。 それは、**「人がいなくなるときこそ、引き継ぎが本気になる」**ということ。
普段は「あの人がいるから大丈夫」で済まされていたことも、 いなくなると、仕組みに変えざるを得ない。 変化しないと困る状況が、人もチームも強くする。
育休もそのひとつだ。
あなたの職場ではどうだろう? “抜けたら困る人”がいるなら、それは「ありがたさ」ではなく「脆さ」かもしれない。
■ 「引き継げる仕事」は、IT投資の成果であり複利で効いてくる
正直、私がやっていた仕事もまだまだ属人的だった。 でも、それを仕組みにする・見える化する・ツールで補うという努力をすれば、 そのたびに**“次が楽になる貯金”**がたまっていく。
IT投資は、その貯金箱を育てるものだと思う。 最初はコストに見えても、やればやるほど複利で効いてくる。
あなたの職場はどうだろう?
- 「これ、毎回誰かがエクセルでやってるよね?」
- 「手順書?あ、誰かが昔書いたっぽいけど…」
そんな状態で回しているとしたら、改善のサイクルは止まっていないだろうか?
空いた時間で、さらに改善を回し続けた会社が、最後に勝つ。
育休もその“時間をつくるきっかけ”になれるのかもしれない。
■ そして、あなたに問いたい
もしあなたが、同じような立場になったらどうするだろう?
- 育休や休職、異動などで一時的に現場を離れるとき
- 誰かに業務を引き継ぐとき
- 「自分がいない間に、何が起きるか」を想像したとき
「仕組みを残していく」って、やっぱり重要なんだと思う。
“いまの自分の仕事、誰かが引き継げる状態になっていますか?” もし「NO」だとしたら、それはなぜでしょう?

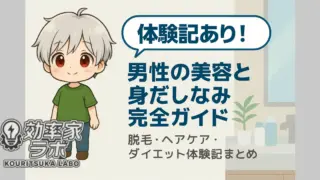

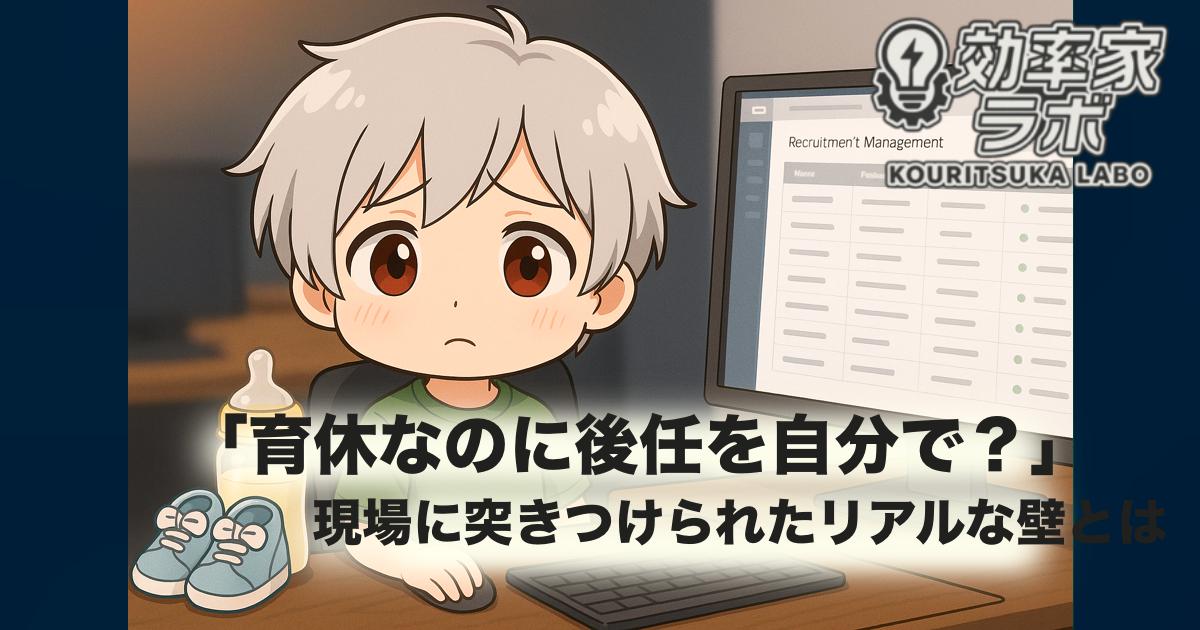

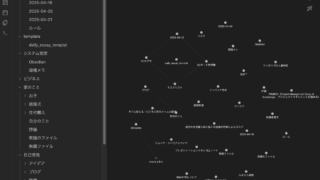
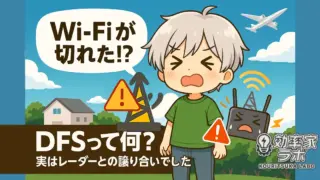




コメント