合わない会社に気づいた“その後”が本番
「この会社、もう無理かもしれない」――そう気づいた瞬間から、本当の意味での“仕事のサバイバル”が始まります。
きっかけは、何かを改善しようとしたときの違和感でした。「このままじゃ、また自分だけが苦労する」と直感したのです。同僚も上司もすでに諦めていて、会社のトップも何も決めない。そんな中で前向きに動こうとすると、浮いてしまう。ここで初めて「自分はこの文化に合っていない」とはっきり自覚しました。
ただ、すぐに辞めるわけにはいきませんでした。私には育休の取得という目標があり、その期間の一部を活用して、転職あるいは自営の準備をするという現実的な戦略があったからです。
だからこそ、「辞めるまでの時間をどう使うか」が大切になったのです。
このブログでは、私が実践してきた「会社に合わないと気づいてから、辞めるまで腐らずに耐えるための工夫」を7つ紹介します。感情論ではなく、仕組みと戦略の話です。
1. 感情を仕組みに逃す:頭の中に置かない
ObsidianやOneNoteも試しましたが、結局私は最初からSharePointに一本化しました。個人ツールより、社内導線と整合する場所に記録を置くことで、2度手間を減らし、使い勝手も向上したからです。
ただし、ここでの目的は「整理」よりも「防御」でした。感情を頭の中にためておくと、怒りや焦りとして発酵してしまう。だからこそ、「書いて、整えて、距離をとる」ことが、自分の感情を守る戦略になったのです。
🔍 補足:心理学的視点からの補足 感情の外在化は「情動の再評価(emotional reappraisal)」という手法に近く、自分の感情を冷静に扱うことで心理的ストレスを減らす効果があります。
2. 質問・依頼に“構造”で対応する:テンプレで自分を守る
何度も同じ質問を受けて疲れていませんか?私はSharePointに業務ナレッジを集約し、「ここを見れば全部ある」状態を作ることで、問い合わせ自体を激減させました。
それまでは、自分を通さないと何も進まない状況が続いていました。営業とサービスの間、顧客とメーカーの間、事務と現場の間――とにかく全部“私を通さないとダメ”。だからこそ、「私がいなくても回る」状態を作りたかったのです。
SharePointのナレッジは、実際に社内で使われ、質問がなくなりました。それが一番の救いでした。やる気のある担当者レベルでは「どうやったら活かせるか?」と考えてくれる人も出てきます。そういう人には、こちらも丁寧に対応するようにしています。
一方で、全く見ようとしない人もいます。それでも問題ありません。重要なのは、“答えがある場所”を整備して、自分の負担を減らすことです。
🔍 補足:組織行動論的な視点 ナレッジ共有のテンプレート化は「知識の暗黙知から形式知への変換」にあたります。これにより属人性を下げ、組織の生産性が上がりやすくなります(SECIモデル参照)。
3. 使われないナレッジにも意味はある:自分のために作る
とはいえ、すべてがうまくいったわけではありません。誰にも読まれない資料もありましたし、引き継ぎ先の人材確保も難航しました。
簡単に「同じことをできる人材が安く手に入る」と思っているフシがあるのも事実です。正直に言えば、「これを全部こなすには年収1000万レベルだぞ」と感じることもありました。
だからこそ、自分のためにナレッジを残す意味は大きい。次に進むときのアピール材料になるし、「私はこれだけ整えていた」という事実は、自分への信頼にもなります。
また、記録の過程で自分の強みや関心領域が見えてきたことも、思わぬ収穫でした。
🔍 補足:キャリア形成論的観点 自分の業務を客観視して記録するプロセスは、「内的キャリア」の再構築につながります。これは“自分は何が得意か、何を大切にしているか”を見直す手段になります。
4. “期待されないこと”に慣れる:無関心の中で折れない
改善提案や効率化のアイデアを出しても、「へえ、すごいね」で終わる文化に心が折れそうになったこともあります。でも、その反応自体が“期待されていない証拠”です。
最初はつらくても、だんだん“無関心でいられる”ことに救われるようになりました。誰からも過剰に頼られず、何かを押し付けられない状態。それは裏を返せば、“自分のペースで淡々と整える自由”があるということでもあります。
🔍 補足:組織心理学的な視点 組織内の「心理的契約」が弱い環境では、自己効力感を保つことが困難になります。しかし、この状態を「自己決定の自由度が高い」と再定義することで、主体性の維持が可能になります。
5. 「残すこと」で距離をとる:個人資産としての記録
私は定時で帰るようになりました。新しい仕事はなるべく受けないようにし、静かにフェードアウトする準備を進めました。
ただ、単に“何もしない”のではなく、「残す」ことを選びました。ナレッジも、資料も、会議の記録も。自分が辞めた後に役立つように整えながら、気持ちの距離も取っていったのです。
🔍 補足:レジリエンス研究の視点 予測可能な将来に向けて準備する行為(プロアクティブ・コーピング)は、職場ストレスに対するレジリエンスを高める戦略の一つです。記録・準備・棚卸しは、心理的安定を助ける行為でもあります。
6. 次の戦いに備える:内側に火を灯し続ける
転職活動は、すぐに本格化しなくてもかまいません。でも、内心で「このままでは終わらない」と決めておくことは重要です。
私はキャリアコンサルタントや転職エージェントとの面談予約を進めています。小さくても前に進んでいる感覚が、心を保つ大事な支えになっています。
🔍 補足:キャリア発達理論の観点 スーパーのライフスパン理論では、キャリアは段階的に発達するとされます。「探索期」における小さなアクション(情報収集や自己理解)は、キャリア成長の土台となるプロセスです。
7. 心の灯を消さない工夫:関心と学びを手放さない
“ここにいても学びがない”と感じることもありました。そんなとき私は、仕事とは直接関係ないけれど「やってみたい」と思った分野の学びを意識的に取り入れるようにしました。
たとえば業務改善に役立ちそうなツールや副業につながるスキルを、少しずつ試し始めました。関心があるものに触れるだけでも、心の灯が消えずに済みます。
🔍 補足:モチベーション理論の観点 デシとライアンの自己決定理論においては、「有能感・自律性・関係性」が満たされることで内発的動機が維持されるとされています。関心ある学びやスキルの習得は、有能感と自律性を刺激し、燃え尽き防止にもつながります。
最後に:あなたの人生に会社は“同居人”でいい
会社は家族でも人生のすべてでもありません。「しばらく一緒に暮らしてる同居人」くらいの距離感でも、まったく問題ないのです。
自分の価値観や働き方に合わないなら、「辞める」以外にも「静かに準備する」という選択肢があります。
腐らず、無理せず、火を絶やさず――。
そんな自己保存戦略が、あなたを次のステージに運んでくれるはずです。
※本記事は筆者の個人的な経験に基づいたものであり、すべての職場に当てはまるわけではありません。制度の活用に関しては各社の規定をよく確認し、信頼できる専門家に相談することをおすすめします。

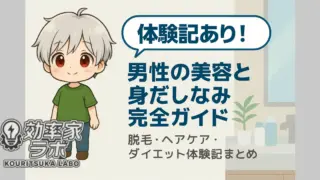

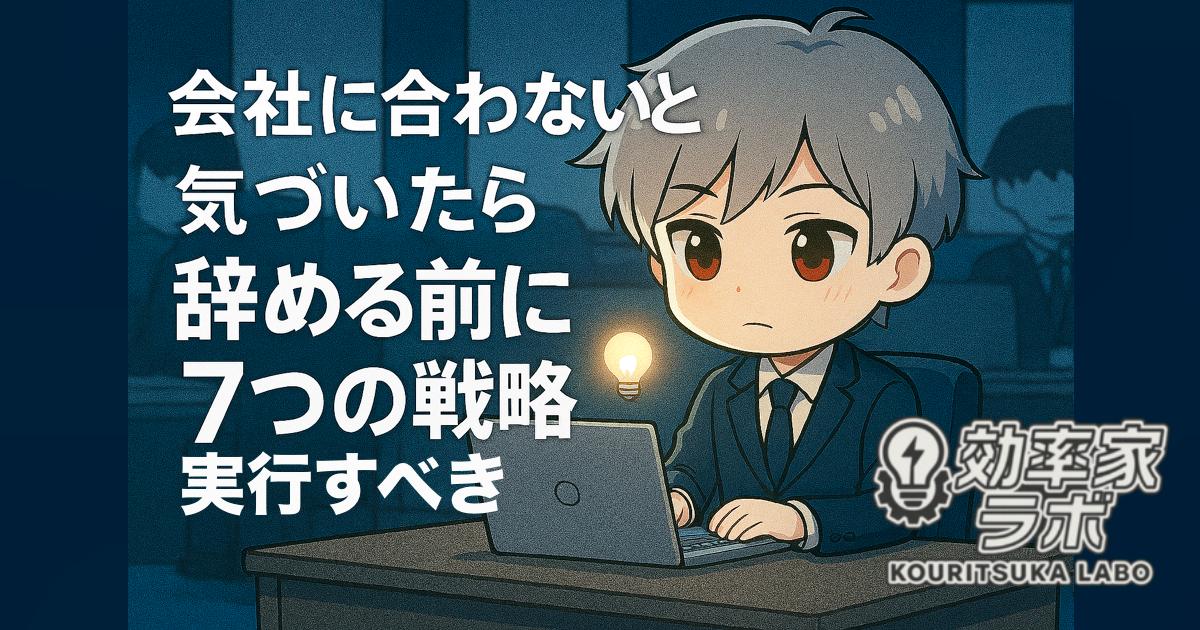
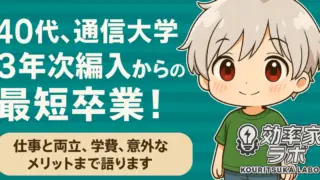



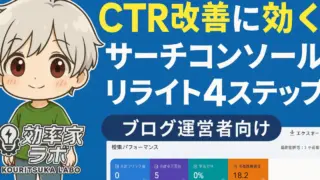


コメント