2027年1月に予定されているiDeCo(個人型確定拠出年金)の大幅改正。企業型DC(企業型確定拠出年金)に加入している共働き世帯にとっては、「制度の壁」がなくなるチャンスです。
本記事では、改正内容の全体像と「マッチング拠出 vs iDeCo」比較、ふるさと納税への影響、そして共働きモデル世帯のシミュレーションを通じて、具体的なインパクトをわかりやすく解説します。
🔧 まずはおさらい|2027年iDeCo制度改正のポイント
✅ 拠出上限の拡大と一本化
- 企業型DCとiDeCoの合算で月62,000円まで拠出可能に。
- 従来の「企業年金の有無で上限が変わる」仕組みは撤廃され、シンプルに。
✅ マッチング拠出の“同額まで”ルールが撤廃
- これまで:会社が1万円出すなら、自分も1万円までしか出せない。
- 改正後:会社が1万円でも、自分で上限まで(最大62,000円)出せるように!
✅ 加入可能年齢が70歳未満に拡大
- 定年後の再雇用や副業収入がある人も、より長く拠出が可能に。
✅ 受取時の「5年ルール」→「10年ルール」に
- 退職金とiDeCoの控除を分けて使うには、10年以上あける必要に。節税戦略に影響。
🤝 iDeCo vs マッチング拠出|どっちが得か?
| 比較項目 | iDeCo | マッチング拠出 |
|---|---|---|
| 税制優遇 | ◎ 全額所得控除 | ◎ 同上 |
| 運用益非課税 | ◎ | ◎ |
| 手数料 | △ 数百円/月 | ◎ 基本無料(会社負担) |
| 運用商品 | ◎ 自由に選べる | △ 会社による |
| 退職・転職時の継続性 | ◎ そのまま継続可能 | △ 移換手続き必要 |
| 管理のしやすさ | △ iDeCoは別口座 | ◎ 企業型DCに一元化可能 |
🎯 判断の分かれ目は?
- 長期勤務予定 & 手数料重視派 → マッチング拠出が有利
- 転職予定あり or 商品にこだわりたい人 → iDeCoが向いてる
👨👩👧 モデルケース|共働き会社員夫婦でどう変わる?
🧑🤝🧑 前提条件
- 夫(40歳)・妻(38歳)ともに会社員
- 企業型DCあり(夫15,000円/月、妻20,000円/月)
- 現在はiDeCoでそれぞれ20,000円/月を拠出
- 世帯年収:約1,200万円(夫婦各600万円)
🔄 改正後の拠出可能額
- 夫:62,000円 − 15,000円 = 47,000円 自由に拠出可能
- 妻:62,000円 − 20,000円 = 42,000円 拠出可能
現状のiDeCo(20,000円/月)から、マッチングに切り替えても → 年間 +50万〜60万円の積立増が可能!
💰 節税効果=“手取りが増える感覚”に
全額所得控除のため、限界税率20%の場合、 年間20万円超の税負担軽減が見込めます。
- 改正前:20,000円×12ヶ月×20% = 48,000円の節税
- 改正後:最大564,000円(夫)+504,000円(妻)拠出 → 約21万円の節税
つまり、実際の収入は変わらなくても、手取りが増える感覚になるんです!
🧮 他制度への影響|ふるさと納税の“盲点”とは?
iDeCoやマッチング拠出のような所得控除が増えると、課税所得が減る。
これにより、ふるさと納税の控除上限額が下がるという影響があります。
❗たとえば:年収400万円・独身の場合、 iDeCo未加入→寄附上限:約43,000円 iDeCo満額(27.6万円)→寄附上限:約35,000円 → 上限が約8,000円減少(シミュレーション例)
2027年の改正で拠出上限が2倍以上になる人は、寄附枠が1〜2万円程度下がる可能性も。
✅ でも安心してください
- iDeCoまたはマッチング拠出で得られる節税額の方が大きい
- ふるさと納税の“控除しきれないリスク”を回避するには、 → 毎年シミュレーションで上限を確認!
他制度への影響は“ふるさと納税”だけじゃない!
実は、課税所得が減ることで影響を受ける制度はほかにもあります。
- 児童手当や高校無償化などの「所得制限ライン」に影響
→ iDeCoまたはマッチング拠出の控除によって“対象外”から“対象内”に復活することがある。 - 医療費控除や配偶者控除なども受けやすくなる可能性
→ 所得が下がることで「配偶者特別控除の対象になる」ケースも - 住民税非課税枠の判定:一部地域での保育料・介護保険料減免に影響
逆に、
- 住宅ローン控除やNISAはiDeCoまたはマッチング拠出と競合しないため、安心して併用OK!
🧭 賢く使いこなすための3ステップ
- 会社の企業型DC制度を確認する
- 掛金はいくら?
- マッチング拠出のルールは?
- 商品ラインナップをチェックする
- 同じ投信があるならマッチングの方が得かも
- NISAやふるさと納税とのバランスを見直す
- 流動性はNISA、節税&老後資金はiDeCo/DCで役割分担!
✍️ まとめ|2027年は「攻めの拠出」が可能になる
これまで複雑だった制度がシンプルに整理され、共働きサラリーマンでも
- 年間100万円を超える拠出
- 年間20万円以上の節税
- 老後資金 × 節税 × 資産形成の三拍子
が現実になります。
もちろん、ふるさと納税の上限が下がるといった細かい影響はあるものの、 トータルで見れば“かなり使える制度”になるのは間違いなし。
ぜひ今のうちに自分の会社の制度・家計状況をチェックして、 2027年以降にベストな選択ができるよう準備しておきましょう!
参考文献・情報源: 厚生労働省「私的年金制度の主な改正事項」(2025年改正法)mhlw.go.jp、令和7年度税制改正大綱の解説kumitateru.jp、楽天証券トウシルmedia.rakuten-sec.net、りそな銀行コラムresonabank.co.jpほか。
- Q限界税率ってなに?
- A
限界税率とは「あと1万円稼いだときに、どれくらい税金がかかるか」の税率です。
たとえば、年収600万円の人で課税所得が400万円くらいの場合、追加の1万円には20%の税金がかかるとされます。これが「限界税率20%」という意味です。
この税率が高い人ほど、iDeCoやふるさと納税などの節税効果が大きくなるため、自分の限界税率をざっくり知っておくとお得な制度を活かしやすくなります。
- Q現行ルール(改正前)はどうだった?
- A
- 旧ルール(現行):
→ 会社掛金の同額までしか自己拠出できない。
→ iDeCoのほうが自己拠出上限が高くて有利なケースあり。 - 新ルール(2027年改正後):
→ 会社掛金を超えて自己拠出OK。
→ 月62,000円まで自由に活用可。
なので、「今までは『同じ掛け金を追加できない』というルールだった」
改正後はその制約がなくなり、制度の選択肢や使い勝手が大きく広がります。 - 旧ルール(現行):
- Q児童手当や高校無償化などの「所得制限ライン」には影響する?
- A
はい。iDeCoやマッチング拠出は“課税所得”を下げるため、対象になる可能性が高まります。
たとえば、児童手当は世帯主の課税所得が一定ラインを超えると支給額が減ったり、ゼロになる制度ですが、iDeCoやマッチング拠出によって課税所得が下がると、“対象内に戻れる”ケースもあります。
例:世帯主の課税所得が970万円 → 年額27.6万円の拠出で942万円に → 所得制限対象内に!
なお、住宅ローン控除のように「課税所得」ではなく「年収ベース」で判定される制度もありますが、多くの“所得制限”は課税所得を基準にしています。
そのため、ギリギリのラインにいる場合は“下げておいた方が得”になることが多いです。
- Q課税所得を下げるのは、世帯主がやる方が有利?それとも夫婦で分担した方が良い?
- A
共働きなら“両方が拠出する”方が有利なことが多いです。
iDeCoやマッチング拠出の所得控除は個人単位で適用されます。たとえば夫婦ともに限界税率20%で同額の拠出をした場合、それぞれが節税効果を受けられるため、ダブルで手取りが増える計算になります。
一方で、児童手当や高校無償化などの「所得制限」は、世帯主(多くは夫)の課税所得で判定されることが多いため、世帯主側の課税所得を優先的に下げるとボーダーを超えずに済む場合があるのです。
✅まとめ
- 節税効果:夫婦それぞれで活用した方が有利
- 所得制限対策:世帯主(判定対象者)の課税所得を重点的に下げるのが有効
- Q節税で「手取りが増える」といっても、拠出額の方が大きくて実際はお金減ってない?
- A
そのとおり。節税で得をするけど、手元のお金(可処分所得)は一時的に減ります。
たとえば、iDeCoに月2万円(年24万円)拠出すると、
限界税率20%の人は**約4.8万円の税金が戻る(または減る)**ことになります。つまり…
- 24万円は老後資金として積み立てに消える
- 4.8万円は税金として払わずに済む
- → 結果、資産は増えるけど、手元のお金は19.2万円減る(=キャッシュフローはマイナス)
✅ でも「損」じゃないの?
→ 長期的には圧倒的にお得です。
- 「税金として消えるお金」を「自分の老後資金」に回せる
- 運用益も非課税で複利が効く
- 引き出せないことで強制的に貯金になる

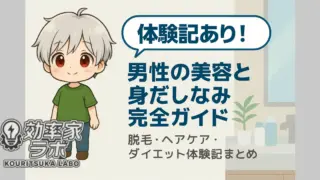

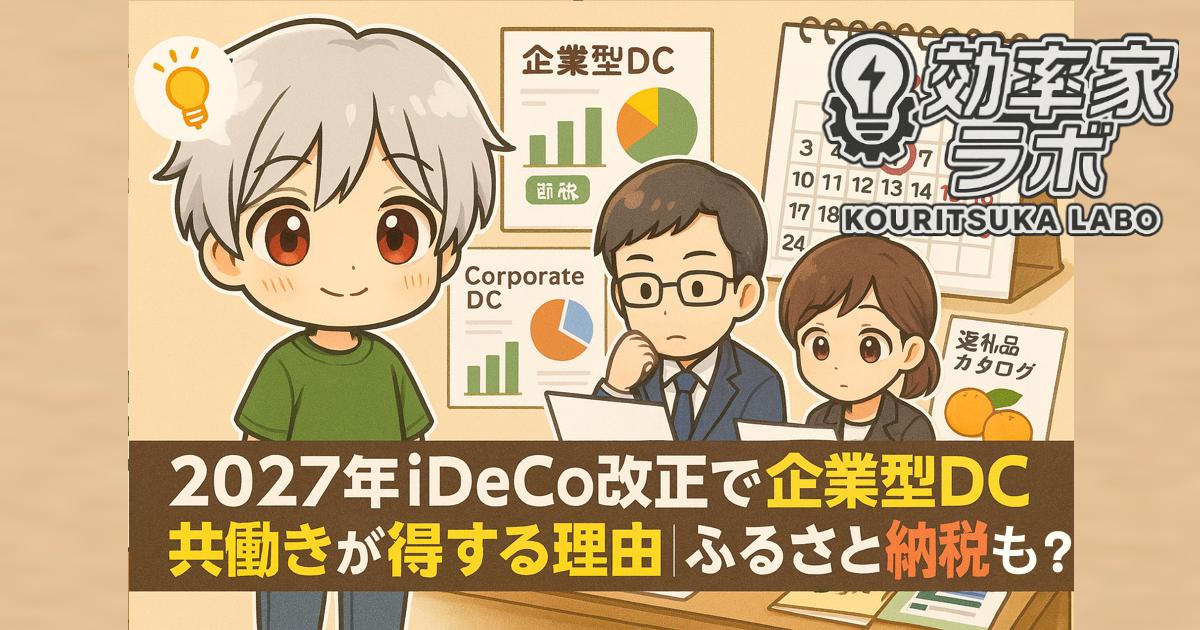



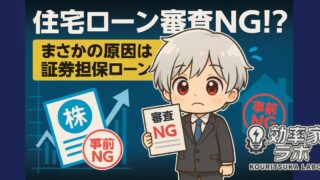
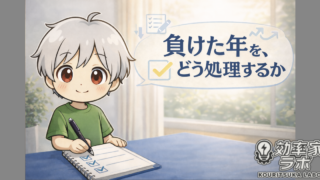



コメント