はじめに
引きこもりから社会復帰した人の話はよく見かけますが、「どうやって抜け出せたのか?」を言語化するのは意外と難しいものです。
僕自身、過去に引きこもっていた時期がありました。今では会社員として働き、結婚して幸せに暮らしていますが、なぜ自分がうまくいったのかはっきり説明できませんでした。
今回は、当時の体験を「対談形式」で振り返りながら整理してみます。
引きこもりの日常
Q:引きこもっていたとき、どんな生活でしたか?
A:ほんとに「ゲーム漬け」です。眠くなったら寝て、起きたらまたゲーム。食事も親が用意してくれるけど、会話はほとんどしない。たまにコンビニに行くぐらいで、1日が終わっていました。
親から何か言われても全部無視。でも「迷惑はかけたくない」という気持ちは心の奥に少しありました。
家の居心地は「良すぎても悪すぎてもダメ」
Q:家庭環境はどうでした?
A:親は優しかったです。そっとしておいてくれるのはありがたかった。当時はむしろ「もっと放置してほしい」くらいに思っていました。
でも、家の居心地が100%良かったわけではありません。僕の地域は当時、創価学会の勧誘がよくあって、それがすごく嫌でした。家にいても落ち着かない感覚があったんです。もしそれがなかったら、家を出たい気持ちはあまり強くならなかったかもしれません。
オフ会がすべてを変えた
Q:脱出のきっかけは何でしたか?
A:ゲーム仲間とのオフ会です。当時やっていたラグナロクオンラインの友達が東京に多くて、「リアルで会おう」という話になったんです。
不安は少しあったけど、それ以上に「楽しみ」が強かった。いつもの仲間と会える!って。
Q:準備のときはどんな気持ちでした?
A:人に会う格好なんて分からなかったです。とりあえず、ボサボサの髪をワックスでガチガチに固めて、「なんとかなるか」って家を出ました(笑)。
行ってみたら想像以上に楽しくて、メンツも良かった。今でも「また会いたい」と思えるぐらいの体験でした。これが大きな分岐点でしたね。
東京での一人暮らしとフリーター生活
Q:その後はどう変わっていきましたか?
A:その流れで東京に一人暮らしを始めました。「大学に行くてい」で上京したんですが、実際は数日しか行かず、すぐにコンビニでバイトを始めました。
最初は短時間のつもりが、気づけばシフトを入りすぎて「主」みたいになってました(笑)。でもこれで社会との接点を持てたのは大きかったです。
その頃は、バイトで稼いだお金でゲーム仲間とメイド喫茶に行ったり、飲みに行ったり。ネットだけでなくリアルの人間関係が広がって、「人見知りなのにコミュ力がついてきたな」と感じるようになりました。mixiのオフ会にもよく参加して、年上・年下関係なく交流する経験は大きかったと思います。
節目が背中を押す
Q:正社員として就職するきっかけは?
A:アパートの更新です。「そろそろちゃんとしないと」と思って就職活動を始めました。きっかけは義務感だけど、バイトや友人関係で「外の世界」に慣れていたからこそスムーズに動けた気がします。
今だから言える学び
Q:今振り返って思うことは?
A:僕の場合は「楽しみが不安を超えた瞬間」が大きな突破口でした。
- 不安をゼロにする必要はない。
- でも「楽しい・会いたい・やってみたい」が不安を上回れば動ける。
そして、家の居心地が100%快適じゃなかったことも一因です。あの勧誘の息苦しさがなかったら、外に出ようとしなかったかもしれません。
引きこもりから脱出するためのヒント
僕の体験をまとめると、次のような要素がカギでした。
- 楽しみを優先する
不安はあっても、「楽しみが勝つ瞬間」があれば外に出られる。 - 外のコミュニティを持つ
ゲーム仲間や趣味の仲間は、社会復帰の架け橋になる。 - 環境の変化を利用する
一人暮らしやアパート更新など、環境の節目は行動のトリガーになる。 - 小さな社会参加から始める
フリーターやアルバイトでも「社会の一員」としての体験が次につながる。 - 家の居心地が“ちょうどよく悪い”ことも大事
居心地が良すぎても変化はない。僕の場合は「勧誘の息苦しさ」が外に出たい動機になった。
おまけ:親の立場でできること
僕の体験は「不安より楽しみが勝った瞬間」が外に出るきっかけでした。けれどもし自分が親の立場だったら?これから親になる自分として、いくつか気づきを書き残しておきたいと思います。
1. 家は安心できるけど、快適すぎない場所に
親が優しいのはありがたい。でも居心地が良すぎるときっかけが掴めず動けなくなる。僕の場合は親への申し訳なさと、地域活動の勧誘が息苦しく「出たい」気持ちが高まった。適度な安心と少しの不便さの両方が必要だと思います。
2. 誘いは軽く、「また今度」で引く
リゼロのスバルの父のように「一緒に行こう」と誘うのは、時にうざい。でも、うざさの裏には愛情がある。大事なのは「強制しない」こと。断られたら「じゃあまた今度な」で軽く流せるスタンスが良いと思います。
3. 小さな外から始める
外食・買い物・短時間のアルバイトなど、いきなり大きな一歩ではなく段階的に。親は選択肢を示すナビ役、決めるのは本人であることが大事だと思います。
4. 「人の目」をきっかけにする
引きこもっている姿を他人に見られたくない気持ちは強い。だから家に友達や親戚が来る予定を伝えるだけでも身なりを整えたり外に出るきっかけになる。サプライズは逆効果になることもあります。
おわりに
引きこもりの背景は人によって違います。だから「万能の処方箋」はありません。
でも、「不安より楽しみを優先する」「家の中だけで完結しないコミュニティを持つ」「環境の変化を味方にする」ことは、多くの人に当てはまるヒントだと思います。
実はこの記事を書こうと思ったのは、X(旧Twitter)で「子どもが引きこもっている」というツイートを見かけたことがきっかけです。自分の体験がそのまま役に立つとは限りませんが、それでも「こういうケースもあるんだ」と誰かが少しでも前を向く材料になれば嬉しいです。
——あなたにとって、不安より楽しみが勝てる瞬間は何ですか?

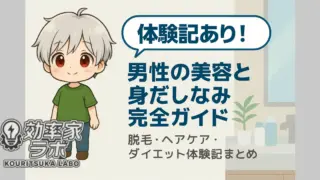


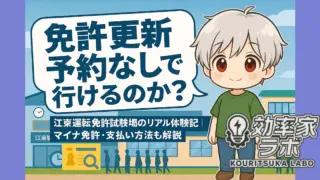






コメント