はじめに:「複利=配当」だと思っていませんか?
投資の世界に足を踏み入れると、必ずと言っていいほど耳にするフレーズがあります。
「複利の力で資産は雪だるま式に増える」。
確かにその通りです。ですが、この言葉が広まる過程で、ある誤解が広がってしまいました。
それは「複利=配当を再投資すること」だという考え方です。
でも、あなたも一度立ち止まって考えてみてください。
株のリターンは配当だけではなく、株価の成長(キャピタルゲイン)からも得られるはずです。
では、配当を出さない企業に投資しても複利は効かないのでしょうか?
答えはもちろん 「No」 です。
本当の複利の本質を知ると、投資の見方が大きく変わります。
複利の本質とは?
まずは複利の正体を整理しましょう。
- 単利:利益を受け取ってしまい、元本は変わらない
- 複利:利益を元本に組み入れ、次の利益を生む
つまり複利とは「利益を利益で増やす仕組み」のことです。
配当を再投資するのも複利、売却益を再投資するのも複利。
ここで大切なのは、「配当があるかどうか」ではなく「利益を再投資しているかどうか」。
これを理解しているかどうかで、投資戦略の幅は大きく変わります。
無配株でも複利は効いている
では、配当を出さない企業に投資するとどうなるのか?
実は、無配株でもしっかり複利は回っています。その仕組みは大きく2つあります。
① 企業内部での複利(内部留保・再投資)
無配株は利益を株主に配当せず、事業拡大に回します。
これがまさに「企業内部で複利を回している」状態です。
たとえばAmazonは無配株、Google(Alphabet)は長い間、無配株でした。
稼いだ利益を研究開発や買収に再投資し、その結果として株価が数倍、数十倍に成長しました。
投資家は配当を受け取らずとも、株価上昇という形で複利の恩恵を受けられたのです。
② 投資家自身が売却益を再投資
もう一つの方法は、株価が値上がりしたところで一部を売却し、その利益を別の投資に回すこと。
これによって「自分で複利を作る」ことができます。
課題は、売却益には課税がかかる点です(日本なら20.315%)。
ですがNISA口座を使えば非課税で再投資できるので、複利効果を最大化できます。
配当株と無配株の複利を比較する
ここで整理のために、配当株と無配株の複利効果を表で比べてみましょう。
| 観点 | 配当株 | 無配株 |
|---|---|---|
| 複利の源泉 | 配当を再投資 | 企業の内部留保+売却益の再投資 |
| 投資家の役割 | 配当を受け取って再投資 | 保有しているだけでも企業が回す |
| 税金 | 配当に課税(NISA除く) | 売却益に課税(NISA除く) |
| メリット | 安定収入・見える安心感 | 高成長を取り込みやすい |
| デメリット | 成長余地が小さい場合も | 利確しないと「絵に描いた餅」 |
つまり、違いは 「複利を誰が回すか」。
- 配当株:投資家が自ら再投資して複利を回す
- 無配株:企業が利益を内部に残して複利を回す
どちらが良いかは投資家の目的や性格によって変わります。
無配株の「複利」をIRで確認する方法
「企業が内部で複利を回している」ことは、IR資料や決算書を読むと確認できます。
具体的には、以下のポイントをチェックしましょう。
- 配当性向
- 配当がゼロ、または低い → 利益を内部留保や成長投資に回している証拠。
- 利益剰余金の推移(バランスシート)
- 利益剰余金が年々積み上がっている → 利益を外部に出さず、内部に蓄えている。
- 投資キャッシュフロー(キャッシュフロー計算書)
- 設備投資や研究開発費、M&Aなどに資金を投じている → 企業が自ら複利を働かせている。
- ROEやROICの改善傾向
- 投下した資本に対するリターンが効率的に高まっている → 内部留保を活かせている。
たとえば、AmazonのIRを見ると「利益剰余金が年々増加」し、「研究開発費が売上の一割以上」になっています。
これはまさに「企業が利益を複利で回している」ことを示す証拠です。
ただし注意点もあります。
内部留保を増やしていても、それを投資に使わず現金として積み上げているだけの企業もあります。
そうした場合は「複利」ではなく「資金の滞留」であり、投資家から批判されることもあるのです。
誤解がもたらす落とし穴
「配当がない株は複利が効かない」
この誤解こそ、多くの投資家を惑わせています。
- 成長株を敬遠してしまう
- 「高配当=正義」と思い込み、割高な株を掴んでしまう
- 配当がない企業を「株主還元しない=悪」と短絡的に考えてしまう
本当に見るべきは「配当の有無」ではなく、利益が再投資されているかどうかです。
業界の常識を疑う
金融業界では「配当再投資こそ複利の王道」と言われがちです。
確かに投資初心者にとって、配当は「目に見えるリターン」であり、複利の説明にも使いやすいからです。
しかし、それは一面の真実にすぎません。
企業の内部留保も立派な複利であり、無配株だからこそ得られる成長の可能性もあります。
一方で「配当を出さない企業は株主軽視ではないか」という反論もあります。
だからこそ、両者の立場を理解しつつ「どの企業が複利を正しく回しているか」を見極めることが重要です。
あなたに問いたいこと
ここで少し自分に問いかけてみましょう。
あなたは「複利を企業に任せる」タイプですか?それとも「自分で複利を回す」タイプですか?
- 安定収入や精神的な安心感を求めるなら配当株
- 成長性を重視し、長期的な株価上昇を狙うなら無配株
- 両方をバランスよく組み合わせるのも選択肢
答えは一つではありません。あなたのライフスタイルや投資方針によって変わるのです。
まとめと次の行動
- 複利は「配当ありき」ではない
- 無配株でも、企業内部での再投資や売却益の再投資によって複利は効いている
- IR資料を読むことで「複利が効いている企業」かどうかを見抜ける
行動提案:
- あなたのポートフォリオにある銘柄の「配当性向」「利益剰余金」「投資キャッシュフロー」をチェックしてみましょう
- NISA口座を活用して、再投資戦略を練り直してみましょう
最後に
「複利=配当」という言葉が一人歩きしたせいで、無配の成長株投資を“ギャンブル”だと誤解する人がいます。
これは金融教育の不足、業界の都合、そして文化的な思い込みが作り出した理不尽です。
本来の複利の意味を理解すれば、あなたの投資の選択肢はもっと広がります。
配当の有無に縛られるのではなく、**「利益が再投資されているかどうか」**で判断する。
それがあなたの未来を変える第一歩です。

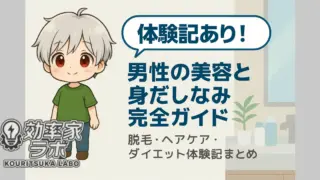





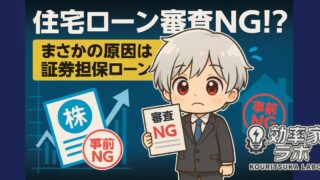
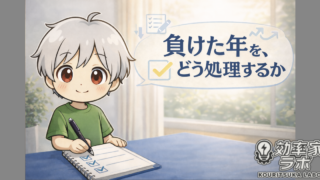


コメント