序章:「昼寝してる漁師」と「チャートを見続けるFIRE民」
ドイツの作家ハインリヒ・ベルが書いた短編『労働意欲を下げるための逸話(Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral)』。
物語の舞台は港町。昼寝している漁師に、旅行者が声をかける。
「もっと漁をすれば、もっと儲かって、もっと豊かになれるのに」と。
しかし漁師は静かに答える。「その結果、海を眺めながらのんびりできるんだろう?今それをしてる。」
このやりとり、今の“FIREブーム”や“効率主義社会”をまるごと皮肉っている。
僕らは「働かなくても生きていける未来」を目指しているのに、なぜかFIREしても働き続ける。
株価を見張り、ブログを書き、SNSで他人の成果をチェックする。
――結局、ベルの漁師よりも忙しい。
第一章:「もっと」が止まらない拡張主義
現代社会のあらゆる場面で“拡張”は正義だ。
会社ではKPI、プライベートでは副業、投資では資産の増加率。
「去年よりも上」「前回よりも速く」「もっと稼ぐ」。
努力の方向が“どれだけ拡大できるか”にすり替わっている。
だが、その果てに待っているのは、「もっと拡張しないと不安になる」という病。
いわば“効率中毒”だ。
本来の目的――“自由な時間”“家族との穏やかな生活”――は、
すでに手に入っているのに、それを“成果”として実感できない。
ベルの漁師が昼寝しているのは、怠けているからではない。
「もう十分だ」と思える心の筋肉があるからだ。
第二章:FIREしても働く3人の現代の漁師たち
では、“もう十分だ”を知るはずのFIRE民たちは、なぜ働き続けるのか。
ここでは、3人の投資家を例に考えてみたい。
いずれも「労働から自由になった後も、なお動き続ける」タイプだ。
● Cisさん ― 拡張の果てでも止まれない人
Cisさんは、若くして巨額の資産を築き上げた伝説的トレーダーだ。
インタビューでは「月収44万円あれば十分」と語り、必要以上に稼ぐことに執着しない姿勢を見せている。
しかし、彼は今でも相場に向かい続ける。
その動機を明言してはいないが、彼の「暇で死にそう」というコメントや発言のトーンからは、
知的興奮と自己効力感こそが労働意欲の源泉であることがうかがえる。
経済的には漁師と同じく「すでに自由」なのに、
精神的には「まだ次の波を待っている」――そんな姿に、拡張主義の宿命が滲む。
● テスタさん ― 社会との接点を再構築する人
テスタさんもまた、FIREを達成したのに、投資講演・社会活動・寄付・メディア出演など、むしろ以前より忙しくしている。
「お金は十分にあるのに、なぜ動くのか?」
本人が明確に「社会との接点が必要」と語ったわけではないが、
その行動全体からは、孤立しないために社会と関わり続ける意志が見える。
彼にとって「働く」とは、利益を得る行為ではなく、社会との関係性を維持する営みに近い。
金銭ではなく、つながりを得るために動き続ける――
これはベルの旅行者が持ちえなかった“成熟した拡張”と思える。
● マサニーさん ― 「再構築」型のFIRE実践者
マサニーさんは、いわゆる“FIRE後も発信する投資家”として知られている。
記事では「暇つぶしで騒いでいる」「時間があるから情報発信している」と語っており、
FIRE生活を「働かない」ではなく「新しい働き方を試す時間」と捉えている節がある。
本人が明言したわけではないが、その姿勢はまさに
“FIREはゴールではなく、働き方の再構築である”
という考え方を体現している。
資産のために働くのではなく、自分の時間をどう使うかを探る労働――
ベルの漁師に最も近い現代型の答えだ。
FIRE民にとっての「昼寝」とは何か
ベルの漁師にとっての昼寝が“満足の象徴”だったように、
現代の投資家にとっての昼寝は“能動的な思索”に置き換わっている。
チャートを眺め、SNSで議論し、情報を発信する――
それは“休息”ではなく、自己の存在を確認するための働きだ。
つまり、FIREとは“労働の終わり”ではなく、
“労働の定義を自分で書き換えること”なのだ。
第三章:「働かない」ことが目的になった時、人は働き始める
FIREの理想は“労働からの解放”。
だが現実のFIRE民の多くは、働くことをやめない。
それは「働かない生活が退屈だから」ではなく、
“働くことが自己表現だから”だ。
ベルの漁師が昼寝を通して「生の実感」を得ていたように、
彼らはトレードや発信を通して自分の存在を確認している。
労働意欲を“下げる”のではなく、“整えている”のだ。
第四章:子育て世代にとっての「漁師的幸福」
共働き家庭にとって、時間は最も高価な資産。
FIREの思想を持っていても、
現実は「仕事・育児・家事」のトリプルバトル。
ここでベルの漁師的視点――“今ここにある満足”――は貴重だ。
子供が笑っている瞬間、
仕事の手を止めて一緒に昼寝する時間、
それは「効率の無駄」ではなく、人生の配当金だ。
拡張主義のゴールは“いつか自由になる”だが、
漁師主義のゴールは“今すでに自由である”。
この差は、親になって初めてわかる。
第五章:僕がFIREしても働き続ける理由
僕自身は、FIREしていない。
共働きの兼業投資家として、日々の仕事と投資を回しながら生きている。
それでも、もしFIREできるレベルになっても、おそらく働き続けると思う。
理由は単純だ。
経済的な自由を得たうえで、やりたいことをやる――それが仕事になりそうだから。
誰かに指示されるためではなく、自分の好奇心で動けるなら、
働くことは「労働」ではなく「表現」になる。
僕にとっての理想は、“働かなくてもいいのに働く”状態。
自由に選べる立場になっても、
新しいサービスを作ったり、面白い人を応援したりしていたい。
つまり、**ベルの漁師の昼寝を、僕は“仕事という形でやりたい”**のだ。
静けさを選ぶ人もいれば、動くことの中で自由を感じる人もいる。
FIREの本質は、どちらを選んでもいいこと――
そして、自分でその選択を意識的にできることだと思う。
終章:自由とは、働く理由を自分で決められること
ハインリヒ・ベルの漁師が笑ったのは、
「働かなくてもいい」からではない。
“なぜ働くのか”を、自分で決めていたからだ。
僕らの多くは、FIREを目指しながらも、
完全な「労働の終わり」を望んでいるわけではない。
本当に欲しいのは、「働くことを選べる自由」だと思う。
Cisさんは、知的興奮のために動き続ける。
テスタさんは、社会とのつながりを保つために動く。
マサニーさんは、働き方そのものを再構築している。
そして僕は、FIREしてもたぶん働く。
経済的な自由を得たうえで、やりたいことをやる。
それが仕事になるだけの話だ。
ベルの漁師が“昼寝”を選んだように、
僕は“仕事”を選ぶ。
静けさの中で満たされる人もいれば、
動くことで生きている実感を得る人もいる。
だから、FIREも、昇進も、副業も――
どれも自由を手にするための手段にすぎない。
本質は、「自分の時間をどう使うか」を自分で選べること。
海を眺めて昼寝してもいい。
新しい事業を立ち上げてもいい。
どちらを選んでも、そこに“満足”があれば、それでいい。
──結局のところ、
「労働意欲を下げるための逸話」は、
“働く意味を自分で定義せよ”というメッセージだったのかもしれない。

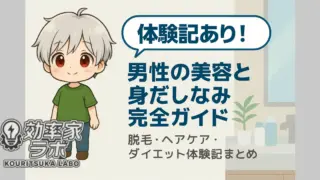

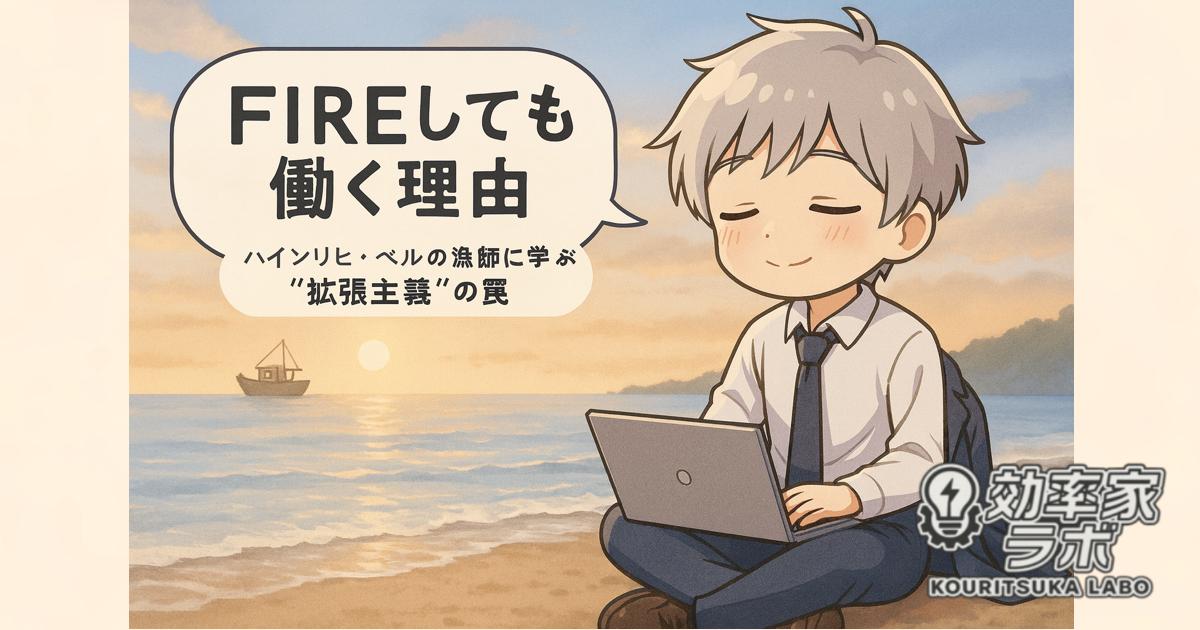
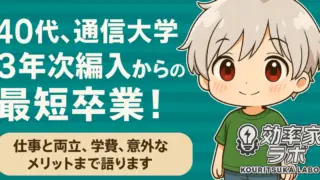



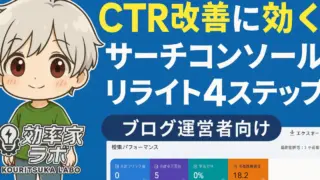

コメント