「あれ…電波届かないんだけど?」
IoTの現場あるあるじゃないですか?
理論上は大丈夫だったはずのLPWA通信が、いざ設置したら「全然つながらんやん…」ってやつ。かく言う僕も、農業法人さん向けの環境センサー導入で、まさにその壁にぶち当たりました。
そんなとき出会ったのが、サーキットデザイン社の無線計算ツール。
しかも全部Webブラウザで使えて、無料・会員登録不要という神仕様。
というわけで今回は、
- 無線初心者でも使えるツールってどんなの?
- 実際にどう使って効果があったの?
- 使ってわかった注意点や落とし穴は?
という3本立てで、僕の“しくじりエピソード”とともに紹介します!
Circuit Design社の計算ツールとは?
こちらの公式サイトで公開されています👇
👉 https://www.circuitdesign.jp/technical/
ざっくり言うと「無線技術者が一度は使うべき計算ツール集」です。
代表的なツール一覧(めっちゃある)
| ツール名 | 使える場面 | コメント |
|---|---|---|
| dB計算ツール | 電力⇔dBm換算 | 単位で混乱する人に◎ |
| フレネルゾーン計算 | 遮蔽物による減衰確認 | 高さ調整の検討に |
| 電波伝搬損失計算 | 距離×周波数で減衰を算出 | LPWA向けに超便利 |
| チャネルプラン計算 | 周波数帯の干渉確認 | 無線LANやLoRa利用時に |
| 通信距離の目安 | 理論値ざっくりチェック | 屋外・屋内パターンあり |
画面はシンプルで使いやすく、スマホでも確認できちゃいます。
実際に使ってみた|農業IoT現場での事例
🌾 ケース1:ビニールハウスでLoRa通信が切れた…
💥 問題:
ハウス内のセンサーから親機まで30m弱。理論上は余裕のはずなのに、扉を閉めると通信が途絶える。
🛠 解決アプローチ:
- 【使ったツール】
- フレネルゾーン計算
- 電波伝搬損失(屋内・屋外モデル)
- 【気づき】
扉と換気用の金属パネルが“フレネルゾーン”の中にガッツリ干渉してた…!
アンテナの高さを1.4m→2.2mに上げたらつながった。
✅ 結果:
計算ツールで障害物の影響を数値化して「なるほど」と納得。
クライアントにも「理論上も改善してます」と説明できて信頼感アップ。
ツールを使うときの“落とし穴”
❌ ミス1:単位変換ミス(dBmとmW)
電力値を入れる時、「あれ?mWで入れたっけ?」ってなるあるある。
→ 単位が合ってるかは最後に必ず確認!
❌ ミス2:フレネルゾーン=中心だけと思い込む
実は“横方向にも広がってる”ので、建物の柱や梁でも影響あり。
→ 特に屋内のLPWAでは注意!
❌ ミス3:環境パラメータをデフォルトのまま使う
屋内の減衰係数を“屋外”で使っちゃうと数値が全然違って設計ミスに…。
まとめ:ツールで“経験則”に裏付けを
無線設計って、感覚や経験に頼りがちですが、
計算ツールを使うだけで「説明できる設計」になるのが最大のメリット。
- 「なぜこの位置か?」に答えられる
- 「通信不安定の理由は何か?」が見えてくる
- 「再設計」にも自信が持てる
無料でここまでできるのはありがたい。
使わない理由、ないでしょ。
使い分け早見表(保存版)
| シーン | まず使うモデル/観点 | 追加で見るもの |
|---|---|---|
| 屋外・短距離・高所LoS | FSPL | フレネル(60%クリア) |
| 屋外・中距離・平坦 | 2波モデル | ハイトパターン/ブレークポイント |
| 屋外・広域 | 奥村・秦 | 地形&建物密度補正、実測で係数調整 |
| 倉庫/ハウス内 | 経験的減衰+2波 | フレネル横ズレ、棚・梁の反射 |
| 共同柱・混在サイト | IM3/遠近 | フィルタ、電力制御、方向性/距離確保 |
❓ FAQ:無線設計でよく出てくる専門用語
- Qフレネルゾーンとは?
- A
送受信を結ぶ直線(見通し線)の周りにできる“電波の通り道”(回折の影響が強い楕円体領域)。第1フレネルゾーンの60%はできるだけ障害物が無いのが理想。
- このゾーン内に障害物があると、電波が大きく減衰する。
- 特に1次フレネルゾーンの確保が重要で、アンテナの高さを上げる理由はここにある。
- Q電波伝搬特性と「自由空間モデル」「2波モデル」 とは?
- A
伝搬損失の代表的な近似モデル。環境で使い分けます。
- 自由空間(FSPL)伝搬:障害物がない理想的な空間での伝搬。距離の2乗に反比例して減衰。
- 2波モデル:電波が地面などで反射し、直接波と反射波が干渉する現実的なモデル。遠距離では減衰が急激に大きくなる。
- 使い分け
- 屋外・高所見通し・短距離 → FSPLで概算
- 平坦地/水面/屋根上など“反射効く系”・中長距離 → 2波モデルが現実に近い
- 設計Tips
「距離だけは余裕」のつもりでも、高さが足りないと2波干渉でドロップしがち。先にブレークポイントとアンテナ高を当てておくと安定します。
- Q3次相互変調混信と遠近問題(Near-Far)とは?
- A
複数の電波が混ざり合ってノイズが発生し、通信に影響する現象。
- 3次相互変調(IM3)混信:強い電波が混ざることで新しい不要波が生じ、受信周波数に重なる問題。
- 遠近問題:近くの強い信号が遠くの弱い信号をかき消してしまう現象。
- 使いどころ(対策)
高ダイナミックレンジ受信機・バンド/SAWフィルタ・チャンネル間隔・送信パワー制御・時間多重(Duty/Listen-Before-Talk)・アンテナ指向性/アイソレーション。 - 設計Tips
屋内実装や基地局の“共用柱”で発生しやすい。**「なぜか現場だけSNRが悪い」**ときは、強電界・IM3・近接強電波のチェックを。
- Qハイトパターン とは?
- A
アンテナの高さ(地上高)を変えたときの受信電界/パス損失の変化。実質、地面反射との干渉が主因で“高さ”に敏感です。ベース局の垂直(仰角)指向性やダウンチルトの議論とセットになることも。
- 使いどころ
屋外LPWA/HaLow/特小などで“何mに立てると一番つながるか”を見積もる。倉庫/ハウスでも梁・棚を避けられる高さを探る。 - 設計Tips
2波モデルのブレークポイント前後で最適高さが動く。まずは**1.5m, 2.5m, 3.5m…**の“段階試験”でピークを探すのが速い。
- 使いどころ
- Q奥村・秦カーブ(Okumura-Hata)とは?
- A
都市・郊外・地方での実測に基づく経験式の大域伝搬モデル。周波数150–1500MHz、距離1–20km、基地局高30–200mなどで妥当。セルラーや広域LPWAの現実的な損失見積に強い。
- 屋外の都市・郊外・山間部などで電波がどれくらい届くかを推定できる。
- モバイル基地局設計やLPWAのカバレッジ検討に活用される。
- 使いどころ
広域リンクのプランニング、エリア可否の早見、建物密度の影響の把握。 - 設計Tips
目安を出すには最強。屋内や超近距離は別モデル併用が無難。サブGHzのLPWAは適合範囲に近く、初期見積り→現地補正が速い。

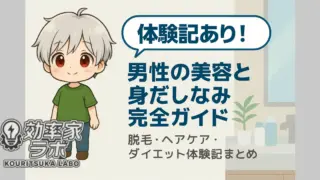



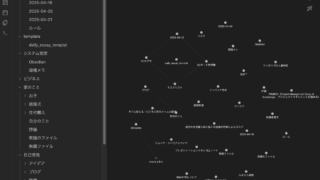
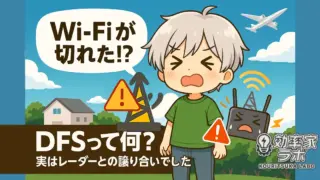




コメント