妊娠が分かったとき、まず感じたのは喜びと同時に大きな不安でした。
特に共働き夫婦や初めての妊娠だと、何をどうサポートすればいいのか迷いますよね。
そんなときに頼りになるのが、夫婦で使える妊娠サポートアプリ。
私たちも妊娠5週からアプリをいくつか導入し、夫婦それぞれの視点で使い分けてきました。この記事では、実際に使って「これは良かった!」と感じた妊娠アプリを、パパ目線でリアルにレビューしながら8つ紹介します。
「どのアプリを選べばいいの?」「夫婦でどう使い分けるのが効果的?」
そんな疑問を持つあなたの参考になる内容になっています。
妊娠中、夫婦でアプリを使うメリットとは?
妊娠が分かった直後、妻がまず「ママninaru」をインストールしました。妊娠中の過ごし方や赤ちゃんの成長について、わかりやすく情報がまとまっていて、すぐに役立ったそうです。私もそれを見て、「パパninaru」を入れました。これは“パパ専用”というだけあって、ママの変化や赤ちゃんの様子を毎週教えてくれるので、自然と関わる意識が持てました。
その後、妻の母からの勧めで「まいにちのたまひよ」も追加。これは専門家監修の情報が毎日届く安心感があり、特に不安が大きくなりがちな妊娠初期にはありがたい存在でした。
さらに、妻はもともと生理周期の記録に「ルナルナ」を使っていて、妊娠が分かってからはアプリ内で「ルナルナベビー」に誘導され、そのまま導入しました。正直、これが最初から一つのアプリで完結してくれたら…と思わなくもありません(笑)。
ちなみに、妊娠8週目には初めての心拍確認ができたのですが、アプリで「そろそろ心拍が分かるかも」といった情報があったことで心の準備ができていました。 また、「ママninaru」の母子手帳の受け取りの時にチェックリストを見ながら持ち物を確認したのがとても役立ちました。
夫婦で使ってみた妊娠サポートアプリ8選(導入時期付き)
私たちが実際に試したアプリと導入したタイミングは以下の通りです。
| アプリ名 | 導入時期 | 目的・印象 |
|---|---|---|
| ママninaru | 妊娠5週目 | 情報が見やすく、妊婦向けの基本がしっかりまとまっている |
| パパninaru | 妊娠5週目 | パパ視点で週ごとのアドバイスが届き、自分ごととして実感しやすい |
| まいにちのたまひよ | 妊娠6〜7週目 | 母親に勧められ導入。専門家監修で安心感あり |
| ルナルナベビー | 妊娠7〜8週目 | 元々のルナルナ利用から自動誘導。TODO表示が便利 |
| その他(トツキトオカ、ままのて、Babyプラス、妊娠週刊パパ) | 不定期 | 目的に応じて試しながら使用。特徴比較のためインストール |
- まいにちのたまひよ(旧:まいたま)
- パパninaru
- トツキトオカ
- ままのて
- ルナルナベビー
- ママninaru
- Babyプラス
- 妊娠週刊パパ
それぞれに特色がありましたが、単純な評価ではなく、「夫婦でどのように分担・活用できたか?」という観点でレビューしています。
妊娠アプリは夫婦でどう使い分ける?3つのおすすめパターン
① 分担型:まいにちのたまひよ+パパninaru
- ママ:まいにちのたまひよ
- パパ:パパninaru
「まいにちのたまひよ」は医師監修の記事が豊富で、体調管理や赤ちゃんの様子を日々学べます。「パパninaru」はその名の通り、パパの立場に特化したアドバイスが週ごとに届くので、気持ちの準備にもなりました。
② 共有型:トツキトオカ
- ママ・パパ:トツキトオカ
このアプリは可愛いイラストや会話機能があり、妊娠期間を日記のように記録できます。夫婦でアカウント共有できるので、「今日はこうだったよ」と話すきっかけにもなりました。
③ ライト型:ママninaru+妊娠週刊パパ
- ママ:ママninaru
- パパ:妊娠週刊パパ
あまりアプリに時間を割けない方向け。シンプルな機能と見やすいUIで、最低限の情報はしっかりキャッチできます。
使ってみて実感したこと
使ってみて特に役立ったのが、「妊娠週数ごとのTODO表示」です。ルナルナベビーは、週ごとに「今こんな状態ですよ」「そろそろこれを準備しておくと安心」など、段階的に教えてくれるのがありがたかったです。
また、「ママninaru」や「パパninaru」は毎週更新されるコラムが充実していて、「へぇ、今は赤ちゃんってこうなんだ」「ママはこんな気持ちなのか」と理解を深める手助けになりました。
我が家では、アプリを見たあとに「今日はこう書いてあったよ」と自然に会話になることも多いです。アプリ画面を見せたりするわけではありませんが、一緒に妊娠の流れを追いかけている感覚が持てて、嬉しい副産物でした。
妊娠アプリの選び方|私たちが重視した3つの基準
アプリを比較・選定する上で、私たちが意識したポイントは以下の3つです。
① 妊娠週数に合わせた情報があるか?
→ 今週の赤ちゃんの状態、やるべき準備などが分かるものは安心感があります。
② パパ向けの具体的なアドバイスがあるか?
→ パパninaruのように、「家事や声かけ」のヒントがあると関わりやすいです。
③ UIがシンプルで、毎日見てもストレスがないか?
→ ごちゃごちゃしすぎると続かないので、デザイン性も意外と重要でした。
- パパ専用アプリは貴重! 妊娠中はどうしてもママ中心の情報が多くなりがち。パパninaruのようなアプリがあると、自分の役割を理解するのに助かります。
- アプリの目的を明確にして選ぶと失敗しない。全てを1つのアプリで補うのは難しいので、情報収集用、記録用など用途を分けるのもアリでした。
- 広告や課金に注意。一部アプリは課金しないと十分な機能が使えなかったり、広告が多くてストレスに感じることもあります。
- 妻が何を使っているかを知るだけでも大きい。夫婦で別々のアプリを使っていても、それをきっかけに話ができれば、充分役立っていると感じました。
※ちなみに我が家ではうまく使い分けられていますが、アプリを複数入れると人によっては情報が煩雑に感じるかもしれません。その場合は、まず一つを決めて試してみるのもおすすめです。
また、私たちは夫婦で分担して複数のアプリを活用しましたが、「同じアプリを2人で共有」や「アプリは1つに絞る」というスタイルも、家庭によっては合っていると思います。
パパninaruを使ってみた感想
私自身、「パパninaru」を入れてみて本当に良かったと思っています。毎日、赤ちゃんの状態が簡潔にまとめられていて、「今日はこんなことが起きてるんだ」と理解する助けになりました。
特にありがたかったのは、「ママは今こう感じているかも」「こんなふうに声をかけてみるといいかも」といった、パパ向けのアドバイスです。そういった情報があることで、自分なりにできることを考えるようになり、家事や料理を手伝う場面でも「これをやっておこう」と自然に思えるようになりました。
もし、妊娠中の方がこの記事を読んでいたら、ぜひパートナーにもアプリを入れてもらうことを強くおすすめします。どんな小さなことでも、パパ自身が妊娠期のプロセスを“自分ごと”として捉えられるきっかけになるはずです。
注意しておきたいポイント
妊娠アプリはあくまで情報サポートの一環であり、すべてを鵜呑みにするのではなく、自分たちのペースで活用することが大切です。
※本記事の内容は個人の体験に基づくものです。体調や症状に不安がある場合は、必ず医師や助産師などの専門家にご相談ください。
まとめ:夫婦で妊娠を支え合う第一歩として
妊娠アプリは「ママだけが使うもの」と思われがちですが、夫婦で協力して使うことで、不安やすれ違いも減らせると実感しました。
もし今、どのアプリを入れようか迷っているパパがいたら、「自分のためのアプリ」を1つ入れてみるのをおすすめします。それだけで妊娠期の関わり方がぐっと変わりますよ。
私たちの体験が、これから妊娠期を迎えるご夫婦の参考になれば嬉しいです。
よくある質問(FAQ)
- Q赤ちゃんの育児で夫と共有できるアプリはありますか?
- A
はい、夫婦で情報共有できるアプリとしては「トツキトオカ」や「ninaruシリーズ(ママninaru/パパninaru)」がおすすめです。妊娠中から出産後まで、赤ちゃんの成長や日々の出来事を共有しやすく、パパが育児に関わる第一歩としても役立ちます。
- Q妊娠したらとったほうがいいアプリはどれですか?
- A
初めての妊娠なら「ママninaru」や「まいにちのたまひよ」がおすすめです。体調管理や出産準備の情報が網羅されており、妊娠週数に応じた具体的なアドバイスも届くので安心です。さらに、パートナーには「パパninaru」も合わせて使ってもらうと、夫婦で妊娠を共有しやすくなります。
- Q2人目の妊娠(経産婦)におすすめの妊娠アプリはありますか?
- A
2人目の妊娠では「ルナルナベビー」や「トツキトオカ」のように、TODO管理や簡単な記録機能があるアプリが人気です。すでに育児経験がある分、手間をかけずに必要な情報を得られるアプリが重宝されます。
- Q妊娠アプリは夫婦で共有するべきですか?
- A
ぜひ共有することをおすすめします。妊娠中はママの心身にさまざまな変化があり、パパとの認識ギャップも生まれやすくなります。アプリを共有することで、同じ情報を元に話せるようになり、不安や誤解を減らせる効果があります。
- Qトツキトオカってどんなアプリですか?
- A
「トツキトオカ」は、赤ちゃんの成長をイラストで可愛く伝えるアプリで、夫婦でアカウントを共有して一緒に妊娠期間を楽しめます。会話機能や記録機能もあり、「今日はこんな日だったね」と自然に会話のきっかけが生まれるのが魅力です。
- Q「まいたま」って夫婦で使えますか?
- A
「まいたま」は現在「まいにちのたまひよ」にリニューアルされています。専門家監修の記事が豊富で、体調や気になる症状について毎日チェックできるため、夫婦で情報を共有するきっかけとしてもおすすめです。

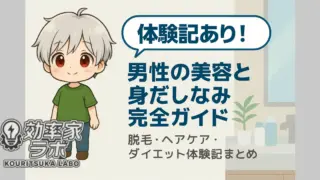










コメント