はじめに:技適マークの誤解、していませんか?
IoT機器や無線機器を扱う際、必ず目にするのが「技適マーク(技術基準適合証明)」です。
このマークがあるだけで、「とりあえず使っても問題ない」と思われがちですが、実際にはそう単純な話ではありません。
とくに近年では、無線モジュールの組み込みやアンテナの交換など、技術的な知識が必要な場面が増えています。
本記事では、技適マークの本当の意味と「工事設計認証」との違い、そして改造が電波法違反になる理由について、やや専門的な観点から解説していきます。
技適制度には2種類ある
まず押さえておきたいのは、「技適」とひとくくりにされがちなこの制度には、2種類の認証制度が存在するという点です。
| 項目 | 技術基準適合証明(通称:技適) | 工事設計認証(通称:設計技適) |
|---|---|---|
| 対象 | 単一の無線機器 | 同一設計の製品群(量産品) |
| 例 | Wi-Fiルーター、Bluetooth機器、ESP32モジュール | スマートメーター、IoTセンサー |
| 認証単位 | 完成品の特定の構成 | 設計図レベルの構成 |
| 改造時の扱い | 認証無効になる可能性大 | 改造不可が前提 |
両者ともに「技適マーク」は付与されますが、認証の対象範囲と前提条件が異なります。
つまり、「技適マークがある=すべて問題なし」とは限らないのです。
なぜアンテナ交換が電波法違反になるのか?
特に注意すべきは、技術基準適合証明を受けた製品においてアンテナを交換する行為です。
このような変更を加えると、以下のリスクが発生します。
- 送信出力の変化
- 周波数特性のズレ
- 指向性の変化による電波干渉の増加
- 他の無線機器や公共通信への影響
技適は、「認証時と同じ構成(アンテナ含む)で使用すること」を前提とした制度であり、それを逸脱すると、認証は無効と見なされます。
その結果、電波法第4条違反となり、**個人でも処罰対象(6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金)**となる可能性があります。
「工事設計認証」との違いと意味合い
工事設計認証は、設計図ベースで量産される製品に対して一括して認証を行う制度です。
こちらは個々の製品に個別認証を取る必要がない代わりに、製品構成を変更する余地がほとんどありません。
組込済みで、エンドユーザーが手を加えられない設計となっていることが前提です。
つまり、技術基準適合証明が「製品構成を守れば自由に使える」タイプなのに対し、
工事設計認証は「そもそも触らせないことで制度的安全を担保している」といえます。
ユーザー責任か?それともメーカー責任か?
ここで疑問が浮かびます。
簡単に改造できるような製品構造や、不適切な販売表示は、果たしてメーカーや販売者に責任はないのか?
法律上は、無線機器を使用して電波を発射する「使用者」が責任を負うとされています。
しかし、以下のような実情も無視できません。
- 「技適あり」と表記しつつ、実際はアンテナが別売りで交換可能
- 技適番号がモジュール部分にしか適用されていない製品
- 技適番号が確認できない中華製品がECサイトで普通に販売されている
- 技適を取得したと称しながら、改造例をSNSで推奨している販売者も存在
📝総務省に確認した際の見解
筆者が総務省の総合通信基盤局に直接確認したところ、
「工事設計認証の場合、製品の取扱説明書や仕様書などに、構成を変更しない旨や技適が付与された条件が明記されていれば、メーカーとしての責任は果たしているとみなす」
との回答がありました。
つまり、販売者・メーカー側が事前に明示しておけば、
**「使用時点で改造したユーザーにすべての責任がある」**という整理が成り立つということです。
📌メーカー視点から見ると
この見解は、メーカー側にとってある種の「安心材料」となるかもしれません。
最低限の説明責任を果たすことで、電波法違反のリスクをユーザー側に明確に切り分けることができるためです。
しかし、実態としては:
- 説明書が存在しない製品(特に海外製)
- 「技適取得済」と書かれているだけで具体的な構成条件が明記されていない
- そもそも誰も取説を読まない
といった状況も多く見られ、トラブルの種は尽きません。
この点において、メーカーの“形式的な正当性”と、ユーザー保護の実態とのギャップがあると言えるでしょう。
「改造したい」場合の選択肢
技術的興味から、無線機器を自作・改造したいと考える技術者もいるでしょう。
その場合、以下の手段が必要になります。
① 再度の技適認証を取得する
- 認証機関への申請・測定・費用(数十万円規模)
- 法人でないと認証自体が困難な場合も
② 無線従事者免許を取得し、試験局として申請する
- アマチュア無線技士などの免許が必要
- 無線局開設申請、試験電波使用届出など手続きが煩雑
個人レベルでは現実的な対応が難しいのが実情です。
まとめ:技適マークは「出発点」であって「免罪符」ではない
- 技適には「技術基準適合証明」と「工事設計認証」の2種類がある
- 改造(特にアンテナ交換)は、電波法違反になる可能性が高い
- 使用者責任を問われるが、販売者・メーカー側の透明性も求められる
- 自作や改造を行う場合は、相応の法的・技術的手続きが必要
技適マークは、安全で公正な無線利用を支える大切な制度ですが、制度の本質を理解せずに盲信してしまうのは危険です。
ユーザー自身が正しい知識を持ち、製品を選ぶ力を持つこと。
それこそが、安心して無線機器を活用するための第一歩となります。
付録:技適番号を確認するには?
技適マークがついていても、「番号が検索できる」かどうかがポイントです。
以下の総務省の公式サイトで、製品に記載された番号を検索してみてください。

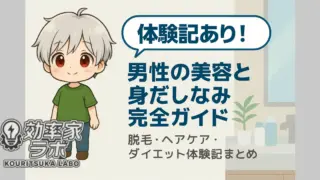


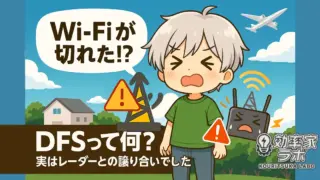

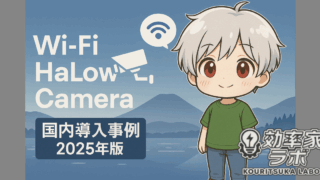
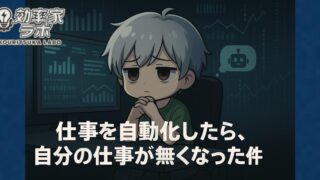
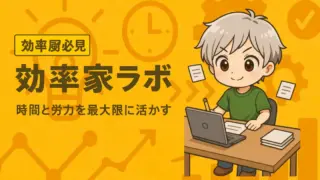


コメント