導入
「Wi-Fi HaLow カメラ」という言葉を耳にしたことはありますか?
最近じわじわと注目されている新しいタイプのネットワークカメラで、まだ家電量販店の棚に並ぶほど普及してはいません。しかし、“法人や自治体の現場ではすでに導入が始まっている” という点で、次世代技術としてチェックしておく価値があります。
この記事では、Wi-Fi HaLow カメラの仕組みや特徴をわかりやすく解説し、さらに国内で入手可能なモデルや法人導入の事例を紹介します。最後に、「家庭でも当たり前に使えるようになる未来像」についても触れていきます。
Wi-Fi HaLow カメラとは?
Wi-Fi HaLow(ハロー)は、IEEE802.11ah という規格名を持つWi-Fiの一種です。最大の特徴は 920MHz帯を使う点。一般的なWi-Fi(2.4GHzや5GHz)より低い周波数帯を使うため、電波が遠くまで飛び、壁や障害物を透過しやすいのが強みです。
- 通信距離:理想条件で1km程度
- 消費電力:従来比で大幅に低く、バッテリー運用やソーラー運用に適合
- 用途:監視カメラ、センサー通信、IoT機器の常時接続など
これらの特性から、Wi-Fi HaLow カメラは「設置場所の自由度が高い監視カメラ」として注目されています。
Wi-Fi HaLow カメラのメリット
1. 広範囲をカバーできる
農場や建設現場など、これまで「電源も通信も届かない」ためにカメラ設置が難しかった場所に導入可能。
2. 消費電力が少ない
ソーラーパネル+バッテリーで動かすケースが現実的に。ケーブル工事が不要になるため、設置コストが大幅に下がります。
3. 通信が安定しやすい
従来のWi-Fiカメラは壁や鉄骨に弱く、通信が途切れやすいという課題がありました。HaLowは障害物を透過しやすいため、設置の自由度が高まります。
日本で入手可能なWi-Fi HaLow カメラ
2025年現在、家庭用に気軽に買えるモデルはまだ少ないものの、法人・自治体向けにはいくつか具体的な製品が登場しています。
Askey CAM2301(Dynalink)
- IEEE802.11ah対応
- 防塵防水(IP66)
- 法人・産業用途として展示会や導入事例あり
Furuno「FWC」クラウド遠隔監視カメラ
- ソーラーパネル一体型で電源工事不要
- LTEとWi-Fi HaLowを併用可能
- 河川や農業、自治体の監視用途で導入開始
いずれも一般消費者向けECサイトで買える段階ではなく、問い合わせや法人契約が前提。
ただし「国内で技適を取得して実用化されている」こと自体が大きな進展です。
Wi-Fi HaLow カメラと従来型Wi-Fiカメラの比較
| 項目 | Wi-Fi HaLow カメラ | 従来型Wi-Fiカメラ |
|---|---|---|
| 通信周波数 | 920MHz帯 | 2.4GHz / 5GHz |
| 通信距離 | 最大1km超 | 数十m〜50m程度 |
| 消費電力 | 低い(バッテリー長持ち) | 比較的高い |
| 障害物透過性 | 強い(壁・木越しでも概ね安定) | 弱い(壁や金属で減衰) |
| 市場普及度 | 法人・産業用途で先行 | 家庭用で一般普及済み |
| 入手性 | 限定的(法人販売中心) | 家電量販店やECで容易に入手 |
この比較を見ると「特性は圧倒的に有利だが、家庭用にはまだ流通していない」という現状がよくわかります。
法人導入事例から見える未来
実際にどんな場所で使われているのでしょうか?
- 河川監視:氾濫リスクを常時モニタリングし、災害時の早期警報につなげる
- 農業分野:遠隔地のハウスや圃場を見守り、人手不足解消や省力化に貢献
- 建設現場:仮設電源やソーラーパネルと組み合わせて、長期間の遠隔監視を実現
これらの導入事例に共通するのは「電源や通信が確保しづらい場所」への対応です。
逆に言えば、この課題は家庭でも少なからず存在します。たとえば庭や駐車場、別宅や倉庫など。
「そこに電源ケーブルを引くのは大変」というケースにピッタリなのがWi-Fi HaLow カメラです。
家庭で使える未来はいつ来る?
現在は法人や自治体向けが中心ですが、技術が成熟し量産効果が出てくれば、家庭用スマートホーム市場にも広がる可能性が高いです。
- 庭や駐車場の監視
- 高齢や子供など家族の見守り
- 災害時の臨時監視
これらのシナリオは、まさに一般家庭に刺さるユースケース。IoT家電の普及とともに「Wi-Fi HaLow カメラ」が当たり前になる未来が見えてきます。
まとめ
Wi-Fi HaLow カメラはまだ黎明期ですが、法人導入はすでに始まりました。
「長距離通信」「省電力」「障害物に強い」 という特性は、従来のWi-Fiカメラでは難しかった課題を解決します。
2025年時点では「法人が先行・家庭はこれから」ですが、スマートホーム市場の進展とともに、数年以内に家庭でも使えるようになる可能性が高いです。
今のうちにこの技術を知っておくことで、次のトレンドを先取りできるかもしれませんね。

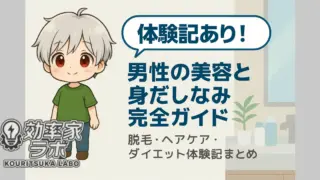



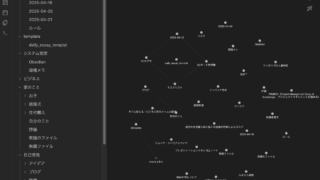
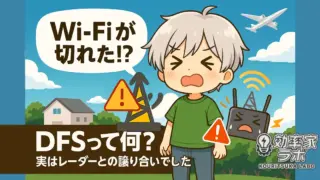




コメント