「40代で通信大学に行くなんて遅い?」「卒業まで続けられる?」そんな不安を感じている方に、40代・社会人の私が3年次編入から卒業までやりきった体験をお伝えします。
40歳からの大学生
「もう若くないし」「仕事が忙しくて勉強なんて無理」――かつての私もそう思っていました。でも、40代にして一念発起。IT専門学校卒という経歴を持つ私が、通信制大学に3年次編入し、最短で卒業するまでの道のりをご紹介します。
IT業界で15年働きながらも、より体系的に学びたいと思い、産業能率大学に編入。
結果、無理なく効率的に単位を取得し、無事に卒業することができました。
本記事では、実際の経験から「最短で卒業するコツ」と「学びを続ける工夫」をまとめています。さらに、通信大学で学ぶことのメリットや予期しなかった恩恵についても詳しく触れていきます。
通信制大学に40代で編入!私が産業能率大学 経営コースを選んだ理由
私はIT専門学校を卒業し、長年IT業界で働いてきました。ただ、実務経験だけでは限界も感じ、「学士」という学位への憧れもありました。
通信制大学を選んだのは、働きながらでも柔軟に学べること。そして、できるだけ早く卒業したかったので3年次編入を選択しました。数ある大学の中で、産業能率大学を選んだ理由は、学費の安さやカリキュラムの柔軟さに加え、社会人にとって現実的な学習環境が整っていたことにあります。
編入にあたっては、保有していたITパスポートやファイナンシャルプランナーなどの資格が、合計で8単位ほど認定され、大きな時短になりました。これにより、自分が取り組むべき学習量が明確になり、モチベーションの維持にもつながりました。会社からの補助も一部あり、費用面でのハードルも低くなったのは、続けやすさに直結しています。
最短卒業のための科目選び
産業能率大学では、3年次編入者に必修科目がなく、かなり自由に科目を選べるのが特長です。これは、自分に合った学び方を追求したい社会人にとって非常にありがたい制度でした。選択肢が多い分、自分の目的や得意・不得意を理解しておくことが大切です。
私の場合、以下のような視点で科目を選びました:
- 得意分野を活かす:もともと興味を持っていたマーケティング関連の科目を多く選択しました。既に多少知識があったため理解が早く、勉強のストレスが少なかったです。
- 学習スタイル重視:産業能率大学では、レポート提出と在宅での試験が中心で、時間と場所に縛られない点が非常に魅力的でした。自分のペースで進めやすく、働きながらの学習にぴったりでした。
- 資格の単位認定:私が保有していたジョブパスやIT関連資格は、複数の単位として認定されました。これにより履修しなければならない科目が減り、卒業までの道のりが短縮されました。
- 仕事との連動:勤務先でマーケティング分野の業務に関わる機会が増えていたこともあり、経営コースの科目を積極的に選びました。実務と学習がリンクすることで、より深い理解につながったと感じています。
さらに、私は「レポート形式か試験形式か」「教科書の内容がどれくらい実務に近いか」など、シラバスをじっくり読み込んで判断しました。忙しい社会人にとって、事前に負荷感を見積もることは非常に重要です。レビューサイトやSNSでの先輩の体験談も参考にしました。
総じて、科目選びの際には「自分の得意分野」「時間効率」「実務との関連性」の3点に加え、「学習のしやすさ」「単位取得のしやすさ」といった観点も持つことで、無理なく計画的に卒業に近づけると感じました。
社会人 通信制大学の卒業率に関するリアルな体感
実際の卒業率は大学や学部によって異なりますが、私の周囲では「最初は意気込んでも中退してしまう人」も一定数いました。特に、社会人になってからの学び直しは、時間確保とモチベーション維持が最大の壁になります。
だからこそ、自分の生活リズムや仕事とのバランスを考えた学習計画が鍵です。実際、産業能率大学では比較的高い卒業率があるようで、サイト上でもアピールされています。レポート中心、在宅試験という柔軟な学習スタイルがその理由だと感じています。他学部や他大学と比較しても、卒業までの道筋が明確だったのはモチベーション維持にもつながりました。
産業能率大学(SANNO)の卒業率
留年しないで卒業する率 大学 69.5% 短大 56.3%SANNOでは、大学・短大ともに毎年1,000人以上の卒業生を輩出しています。
産業能率大学HP https://www.sanno.ac.jp/tukyo/feature/reason.html
また、大学入学者の約7割を占める3年次編入学生の標準学習期間(2年間)での卒業率は69.5%で(2025年3月度卒業生)、短大1年次入学者の標準学習期間(2年間)での卒業率は56.3%であり(2025年3月度卒業生)、高い卒業率を誇っています。
※「標準学習期間」とは留年を含まない学習期間を意味します。
通信制大学おすすめの学部ジャンル(40代に人気)
私は今回産業能率大学の経営コースを選択しましたが、産業能率大学以外でも通信制大学はたくさんありました。
学び直しを検討する40代の方におすすめの学部ジャンルは、以下の通りです:
- 経営・ビジネス系(例:経営学部、商学部):仕事と直結しやすく、汎用性が高い
- 心理学系:キャリアチェンジや対人関係の理解に役立つ
- 福祉・介護系:今後の社会的ニーズが高く、資格取得にもつながる
- 情報・IT系:IT再教育やキャリアアップを目的とした人に
40代であれば、既に実務経験がある分、学びの応用やアウトプットがしやすい点が大きな強みです。通信制大学なら、自分の関心やキャリアと照らし合わせながら無理なく選べます。
ミスから学んだ履修の注意点
一度だけ、履修した科目が翌年廃止になり、テストを受けられない事態に。通知はあったのに見落としたのが原因でした。これは、忙しさにかまけて大学からの連絡をチェックしていなかったことが大きな失敗です。
この経験から、大学からの連絡は必ず確認し、履修変更の情報には注意するように心がけました。特に、履修登録時期の直前や期末が近づく頃は、こまめに大学ポータルサイトを確認するようにしています。周囲の学生との情報交換もミス防止につながります。
仕事と両立する学習スタイル
平日は仕事に集中。週末のまとまった時間に学習を一気に進めるスタイルが自分には合っていました。通勤中のすきま時間に資料を読んだり、音声読み上げアプリを使って復習するなど、小さな工夫も積み重ねました。
特別なアプリやツールは使わず、教科書をしっかり読み込む地道な方法で進めました。知的好奇心が刺激され、学ぶこと自体が楽しくなったのも大きな収穫です。加えて、家族の協力も大きかったです。妻が学習時間を確保できるよう家事を調整してくれたことには、感謝しかありません。
学生の身分で受けられる「学割」も意外なメリットでした。Apple製品やMicrosoft Office、Evernoteなどの割引を活用し、間接的に学習時間を確保する手助けになりました。公共施設や図書館の利用も、落ち着いて勉強する環境として重宝しました。
試験対策=レポートを制すること
産業能率大学では過去問の提供がなく、試験対策としてはレポートが鍵になります。しっかりと教科書を読み、レポートで理解を深めることで自然と試験にも対応できました。レポートを書く中で知識の整理ができ、記述力も向上します。
また、提出したレポートに対する講師からのフィードバックも学習に役立ちました。どこが弱点か、どこを深掘りすべきかが明確になり、次回の学習に活かせるのです。学びながら考える力が身に付くのが、レポート学習の良さだと実感しました。
自己学習中心でしたが、基礎を固めることの大切さを実感しました。場合によっては、オンラインでの同級生との情報交換も励みになりました。
卒業後に見えた新たな道
最短卒業後、さらに学習意欲が高まり、大学院進学も視野に入っています。通学が必要な点は悩みどころですが、補助金制度もあるようなので調査中です。特に、社会人を対象とした夜間・週末講義のある大学院や、オンライン対応しているプログラムも選択肢に含めて検討しています。
また、今回の学びを通して「学ぶこと自体が楽しい」という価値観に気づいたのは大きな変化でした。キャリアアップだけでなく、自己成長のための学びを継続したいと思えるようになりました。
まとめ:40代からでも遅くない!
通信大学は、40代・社会人でも現実的な選択肢です。自分に合った学習スタイルと計画、そして周囲の協力があれば、年齢を理由に学びを諦める必要はありません。今からでも、遅すぎるということは決してありません。
「働きながらでも学びたい」「学士が欲しい」と思っている方の背中を押せたら幸いです。これからの人生で何か新しいことに挑戦したい方にも、通信大学での学びは確かな一歩になるはずです。
▶ 私の通信制大学体験談をnoteにもまとめました
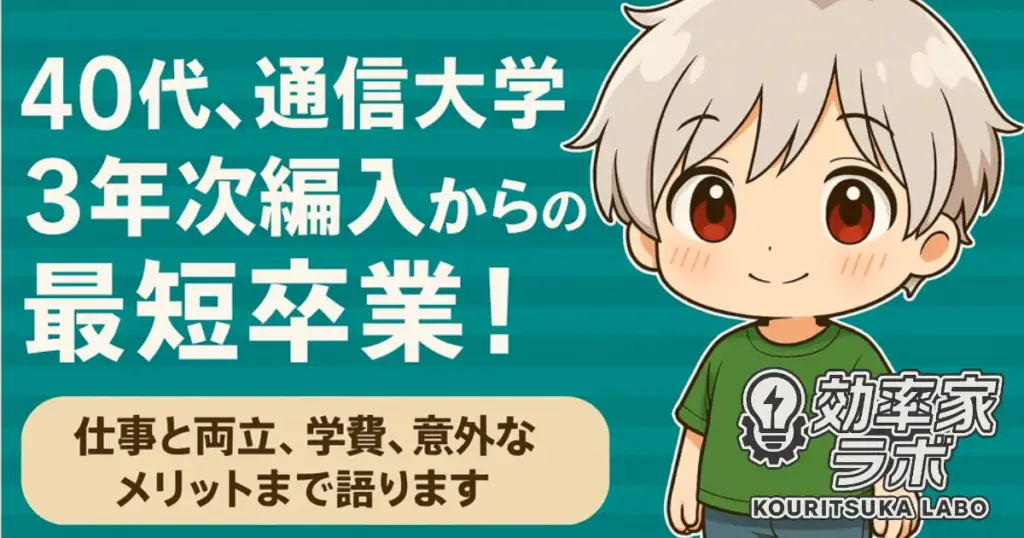
- 40代で編入した私が感じた通信制大学のリアル(note)
- 40代から通信大学へ!3年次編入で最短卒業する方法と体験談
- 学び直し失敗談:大学院の単科履修をやめた理由
- 通信制大学を卒業した40代のその後|キャリア・学び・家族がこう変わった話
- 通信制大学の費用・制度を徹底比較|卒業までのロードマップと失敗回避策(作成予定)
- 40代社会人が本気で選ぶ!おすすめ通信制大学ランキング【主観あり】(作成予定)

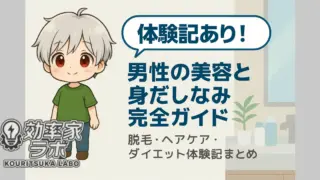

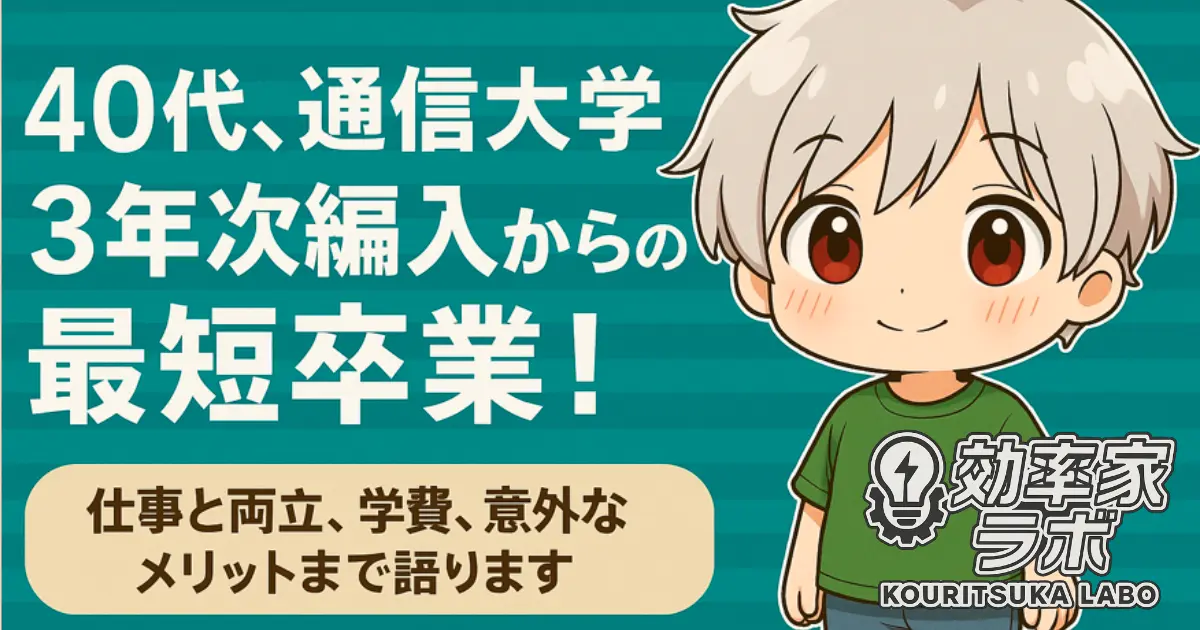
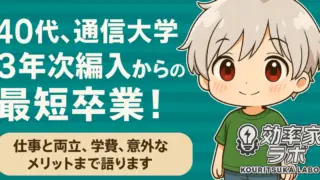



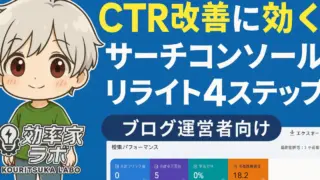

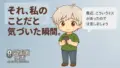
コメント